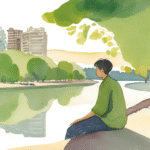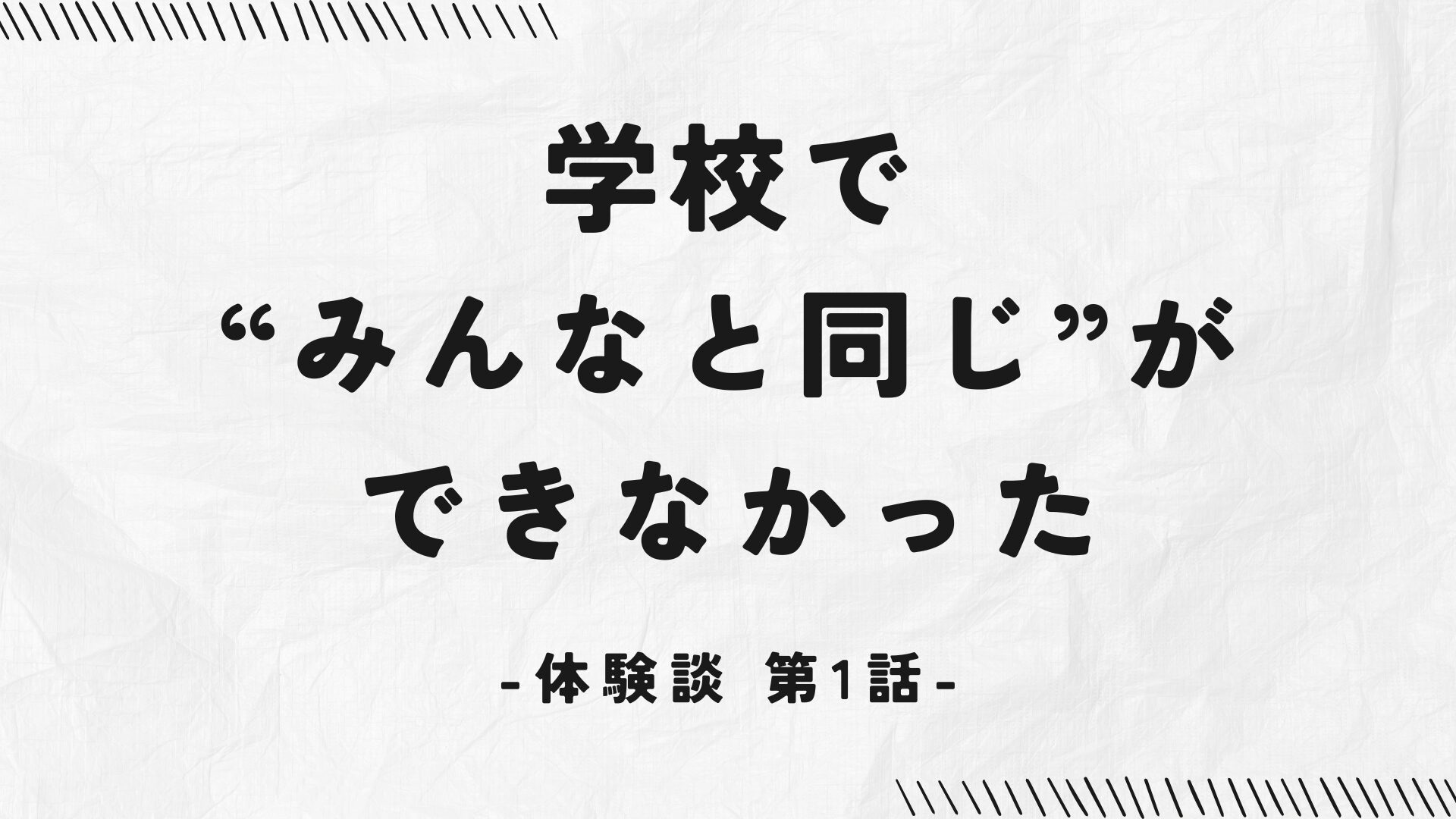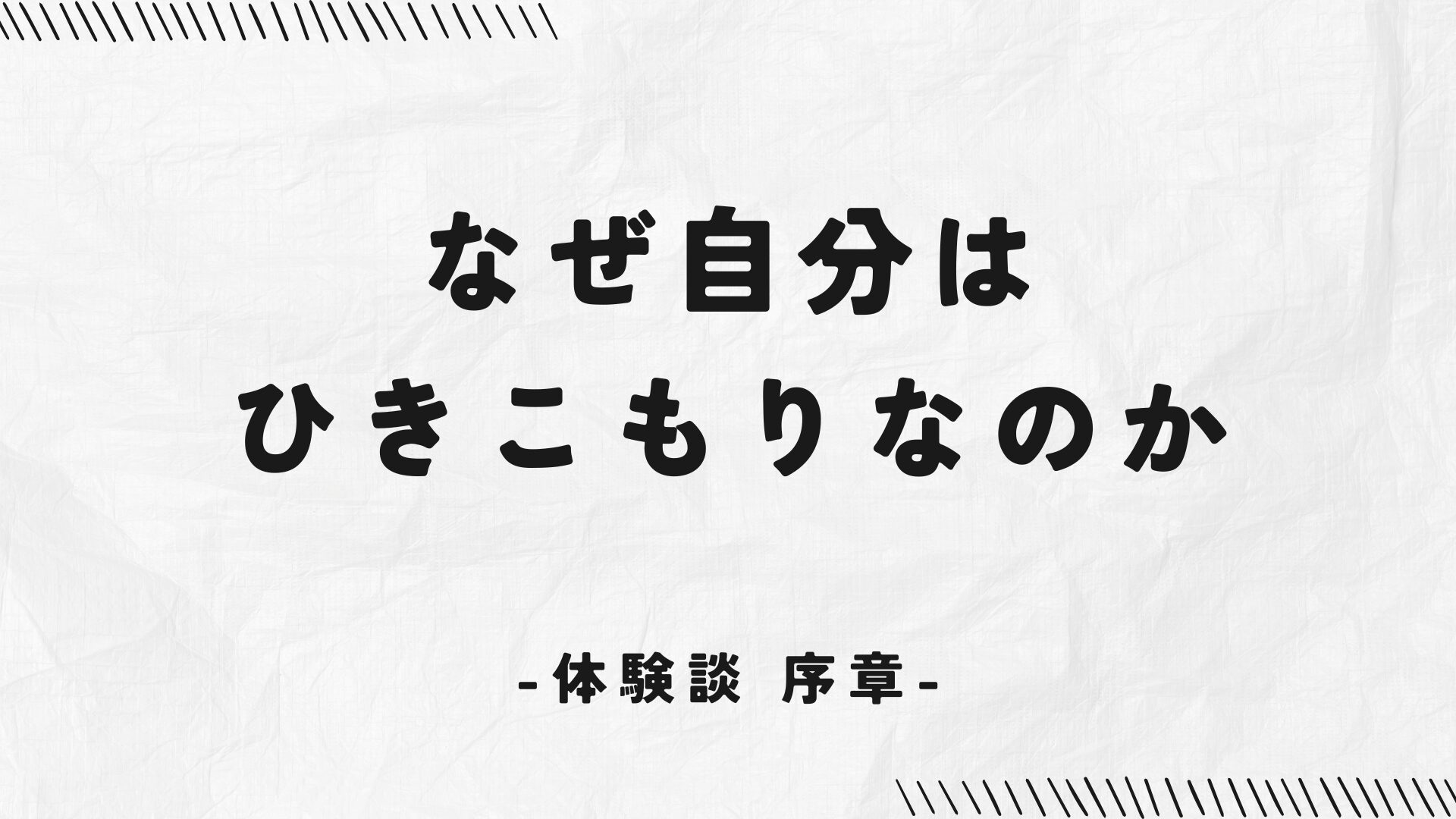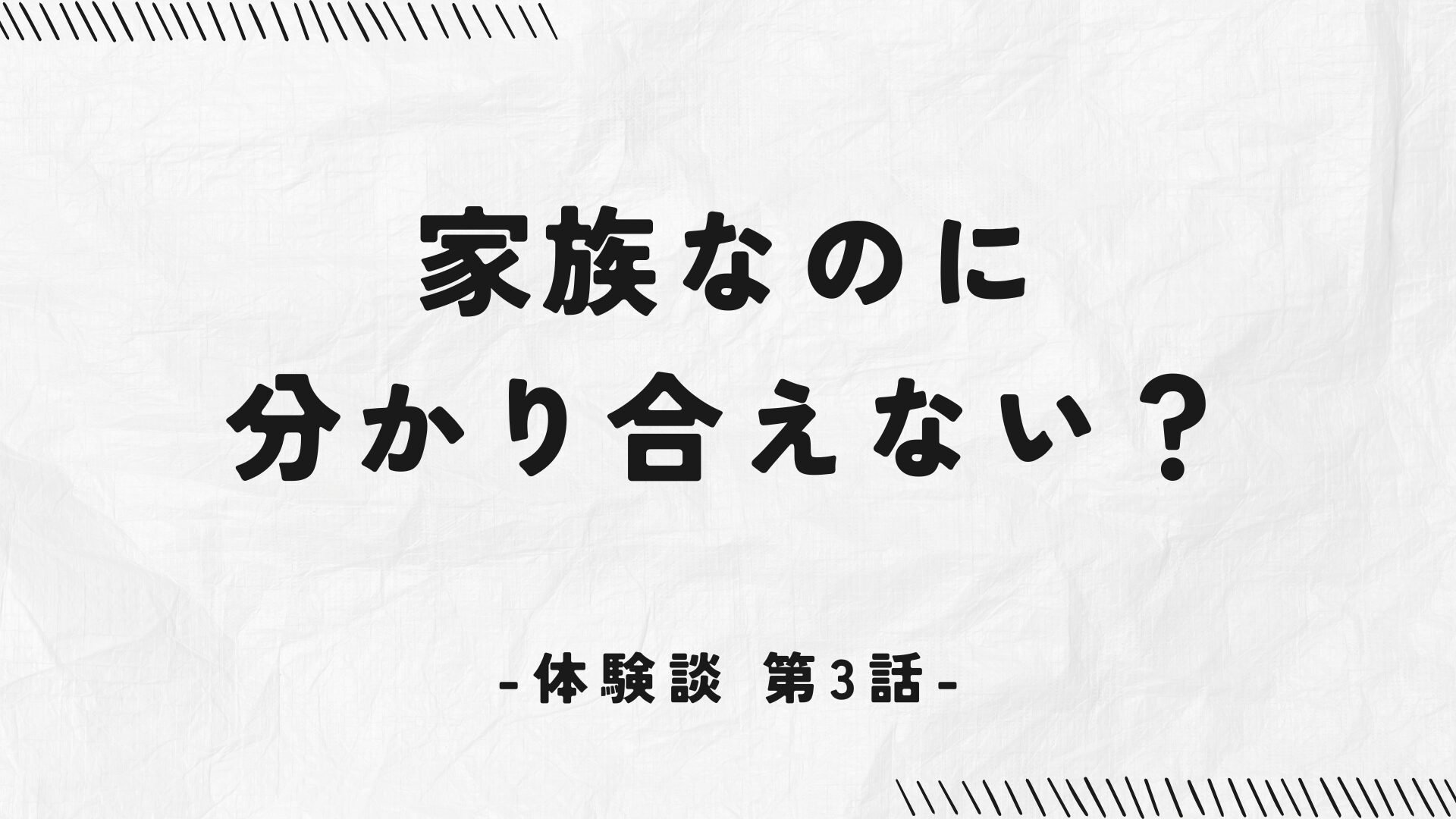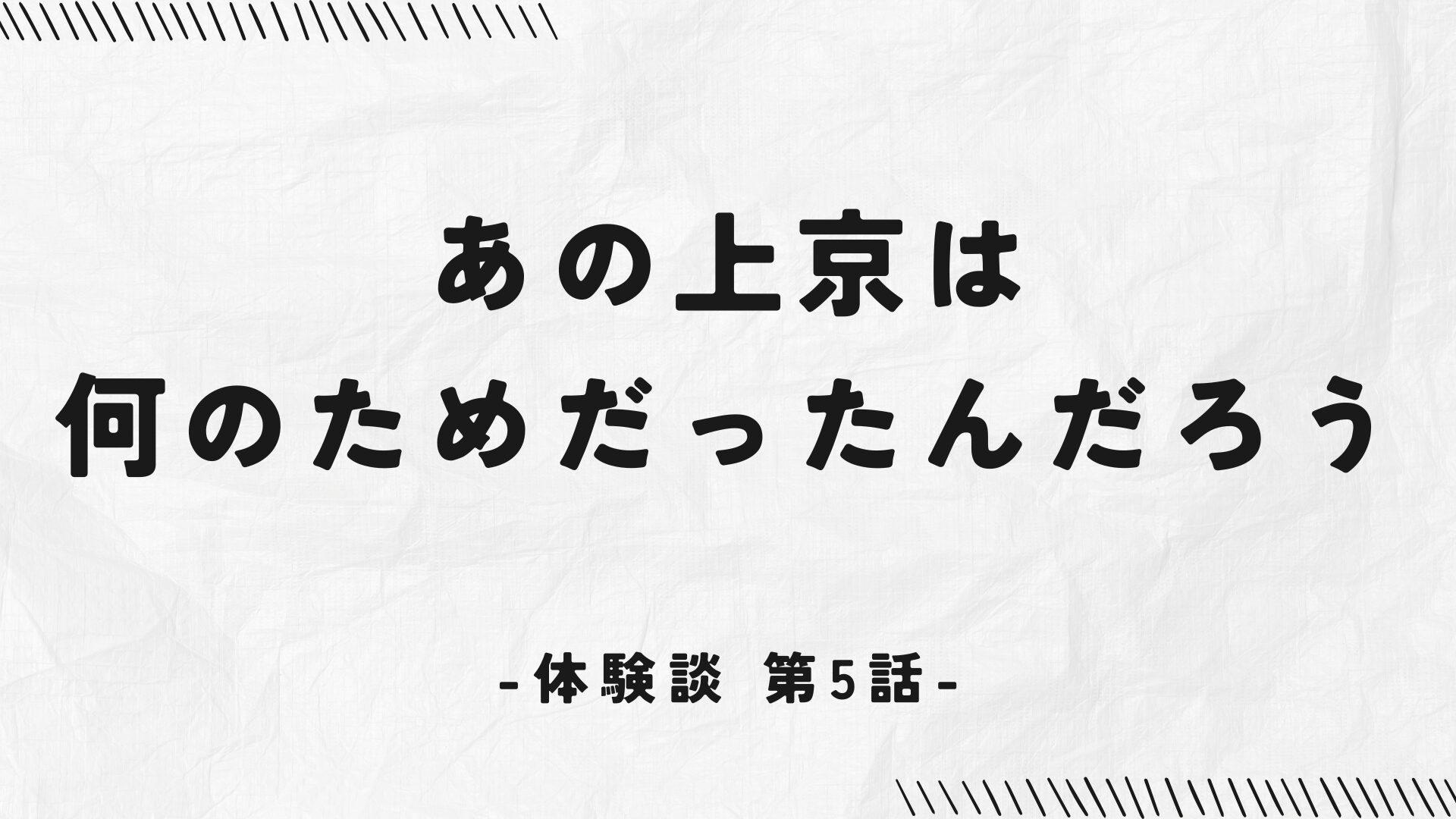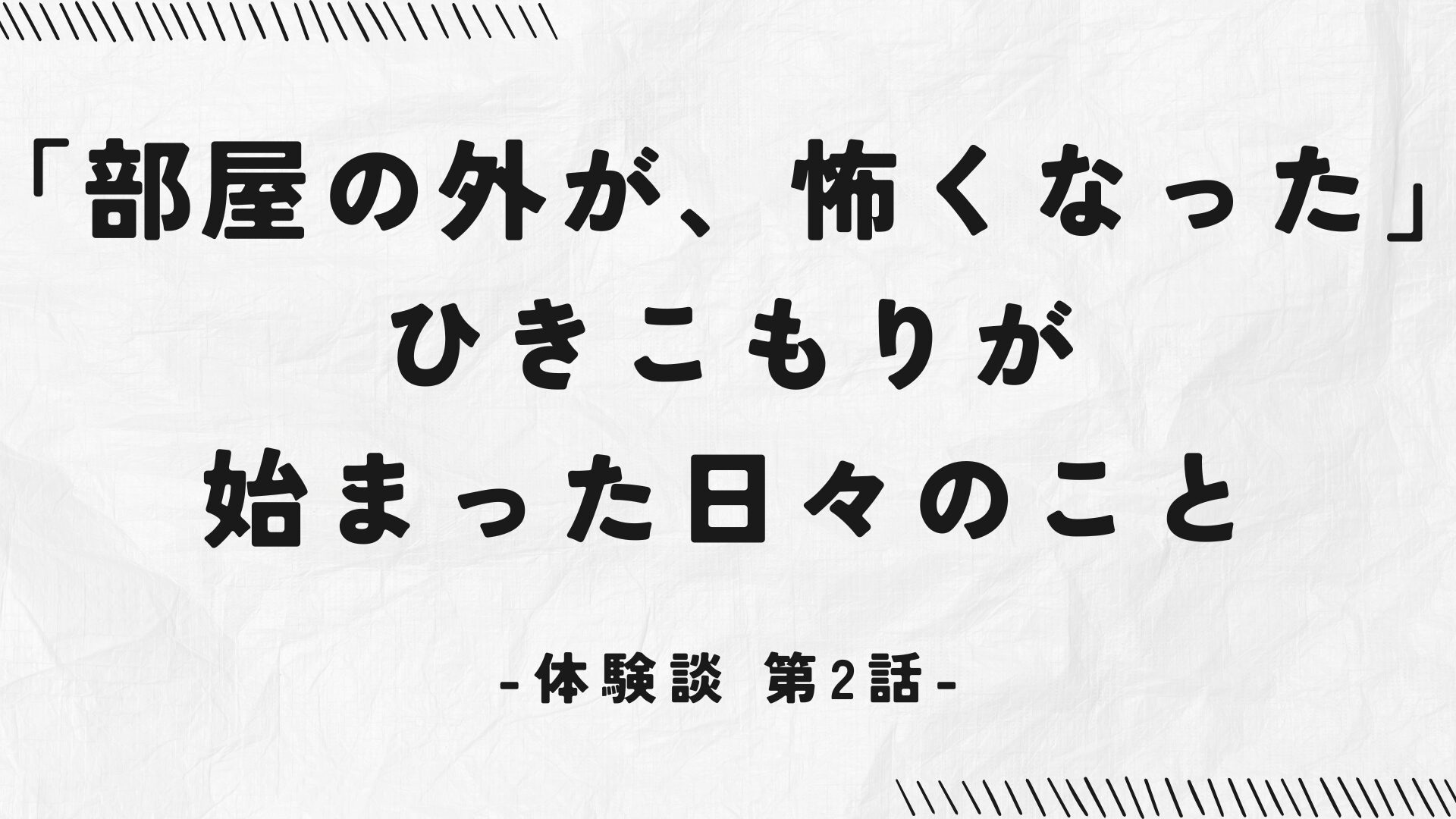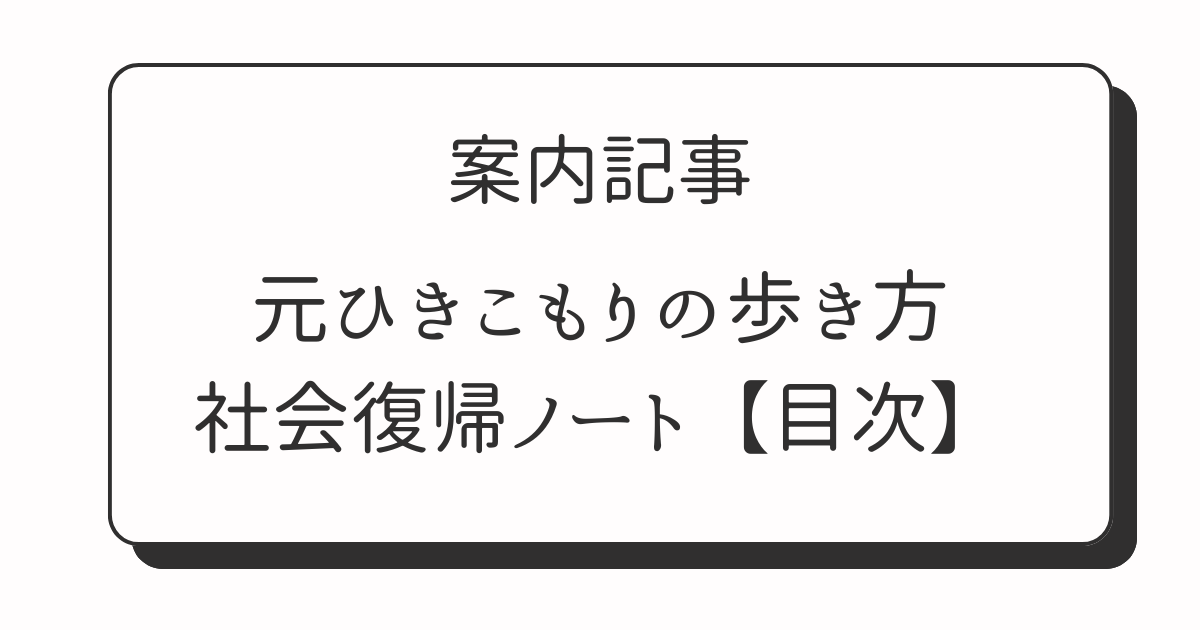第4話:他人の目が、いつも刺さるように感じていた
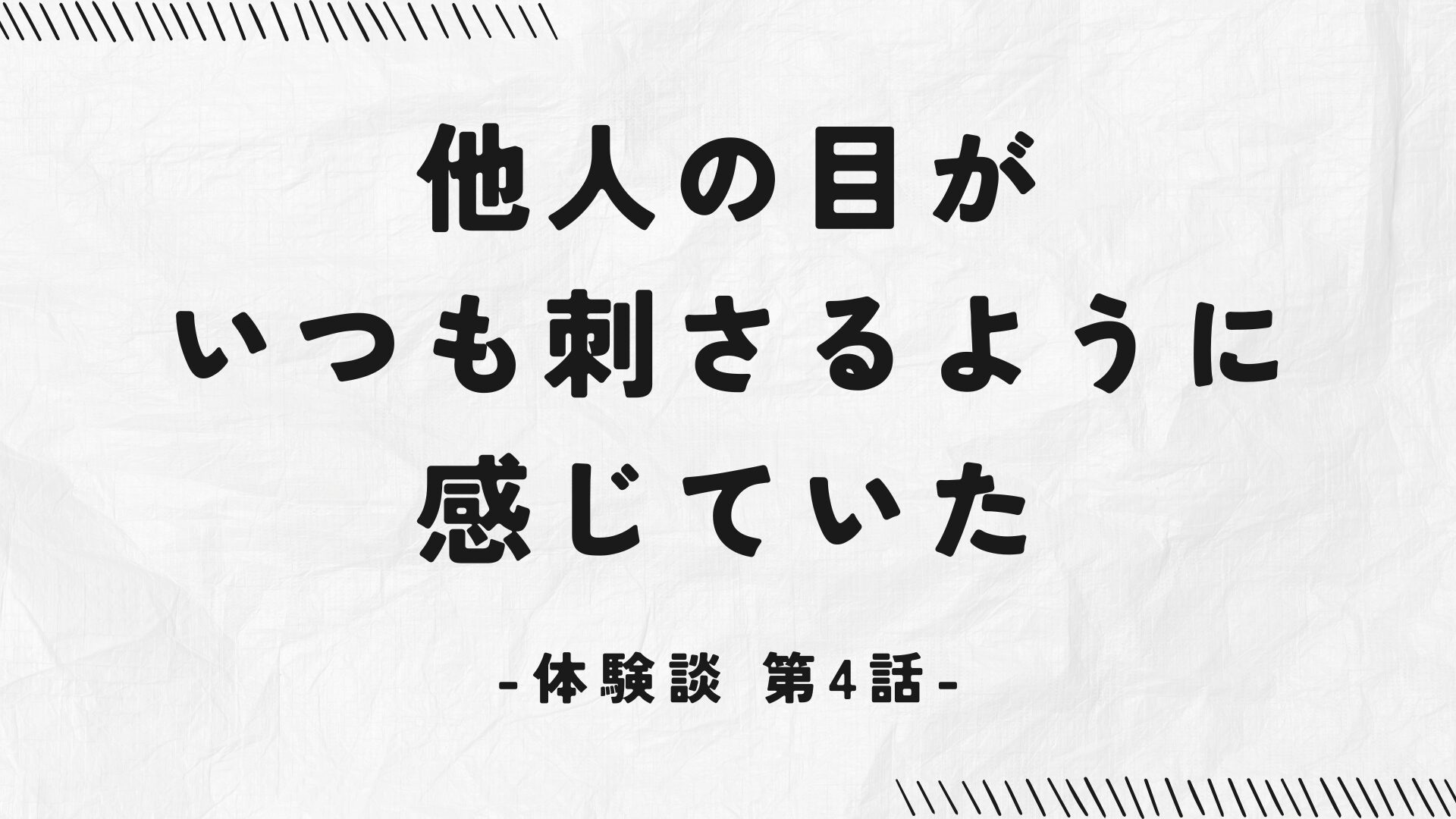
ー第1章:ひきこもりのはじまりー
高校で感じた「視線の恐怖」
自分を見られているような感覚
高校に通っていた時、自分は他人の目がとても気になっていました。今思えば、きっと自意識過剰だったのだと思います。けれど当時は、教室にいても、廊下を歩いていても、部活中でも、なぜか誰かの視線を常に感じていたんです。
他人は自分のことにそんなに興味を持っていないものです。そんなに気にしなくていい。でも高校生の自分は気になってしょうがなかった。
小さな反応にも敏感になっていた
その「視線」は、じっと見られているわけではなくても、自分がどう思われているかを常に気にしてしまうような感覚でした。
周囲の会話の一部が、自分に向けられたもののように感じたり、小さな笑い声にさえ反応してしまったり。学校という空間が、特別に緊張する場所になっていきました。
学校だけじゃない、外の世界でも
家の外でも強まった視線への意識
学校に行かなくなり、家に籠るようになってからも、視線に対する過敏さは消えませんでした。むしろ、外に出たときの方が強く感じるようになったのです。
「不登校」という意識が不安を増幅させた
ちょっと買い物に出ただけで、「この子は学校に行っていないのに何をしてるんだろう?」そんなふうに見られている気がして、足早に帰ってくることも多くなりました。
これは、不登校であることに対する罪悪感が、自分の中にあったからだと思います。自分でも「学校に行っていないのは良くないことだ」と思い込んでいたからこそ、他人の目が刺さるように感じていたのかもしれません。
それでも、漫画が好きだった自分は、どうしても読みたくて、ブックオフまで自転車で行って立ち読みをすることがありました。店内に入るまでは緊張していましたが、漫画の世界に入ってしまえば不安を忘れることができたのを覚えています。
そんな時間が、気持ちのバランスを保つためのささやかな逃げ場だったのかもしれません。
気づかないふり、平気なふり
感情に向き合うことの難しさ
そんな風に感じていた自分の気持ちに、当時は向き合うことができませんでした。「なんでこんなに気にしてしまうんだろう」と戸惑いながらも、その感情を直視するのが怖くて、見て見ぬふりをしていたんです。
心の中にある不安や戸惑いは、自分でもうまく言葉にできないものでした。誰かに話す勇気もなかったし、そもそも何を話せばいいのかも分からなかった。
周囲への「平気なふり」と本音のギャップ
周囲にはなるべく平気なふりをして、感情を表に出さないようにしていました。でも本当は、不安や恥ずかしさがずっと心の中にありました。
「ちゃんと向き合っていれば、また違った結果になったかもしれない」──そう思うこともあります。でも、当時の自分にはそれができるだけの余裕も、方法も、知識もなかった。だから、逃げるしかなかったんです。
自分で選んだこと、自分にしか変えられないこと
「逃げた選択」も自分の選択だった
今になって思うのは、「逃げた」選択も、自分が選んだことだったということです。
周りのせいにするのは簡単ですが、それでは何も変わりません。選択肢が狭かったのは、自分自身がそれ以外の道を知らなかったから。
何が正解かも分からず、不安や戸惑いの中で、それでも自分なりに必死に選んだ道でした。たとえその結果が「逃げる」ことだったとしても、自分なりに精一杯考えた末の選択であり、生き延びるために必要な一歩だったのだと思います。
誰かに助けを求めることもできず、自分なりに選んだ唯一の方法だった。そう思えば、自分を責める必要なんてなかったんだと、思えるようになりました。
未来を形づくるのは今の自分
過去の自分を責める気持ちはありません。あの時の自分は、自分にできる精一杯の選択をしたんです。周囲にどう見られるかばかりを気にして、行動に移せなかったことも含めて、すべてが今の自分の形を作っているのだと思います。
大事なのは、これからの自分が、どんな選択肢を持てるようになるか。そのためには、日々の中で少しずつ視野を広げていくことが大切です。
選択肢を広げるためには、知識を持つこと。見聞を広げること。それが、自分の未来を形作る一歩になるのだと思います。
まとめ・過去の自分、読者へのひとこと
あの頃の自分に「気にしすぎなくて大丈夫だよ」と声をかけてあげたい気持ちです。でも、きっとその時の自分には、届かなかったでしょう。
だからこそ、今悩んでいる誰かに伝えたい。
「過去の選択を責めなくてもいい。未来の自分は、今のあなたが形づくるものだから」
◀【目次】はこちら→ 元ひきこもりの歩き方|社会復帰ノート
◀【第3話】はこちら→家族なのに、分かり合えない?
▶【第5話】はこちら→あの上京は、何のためだったんだろう