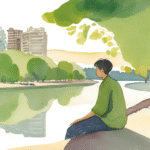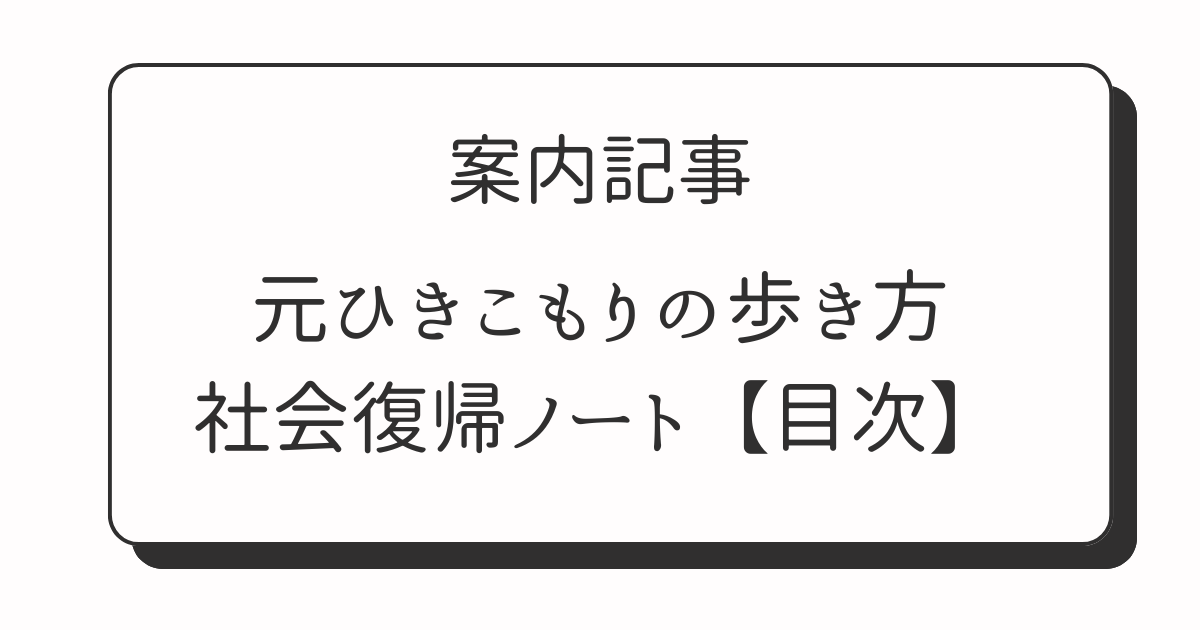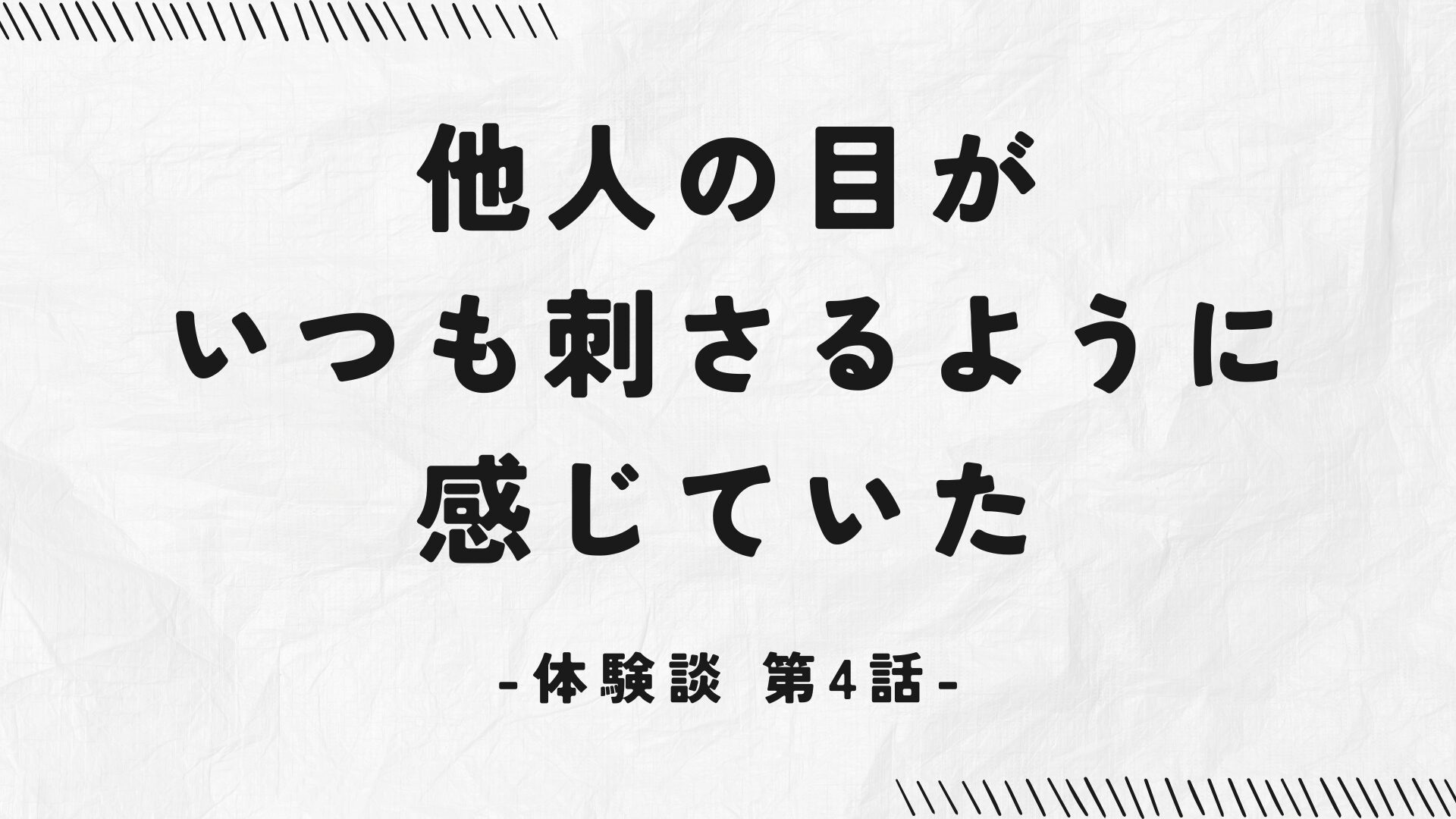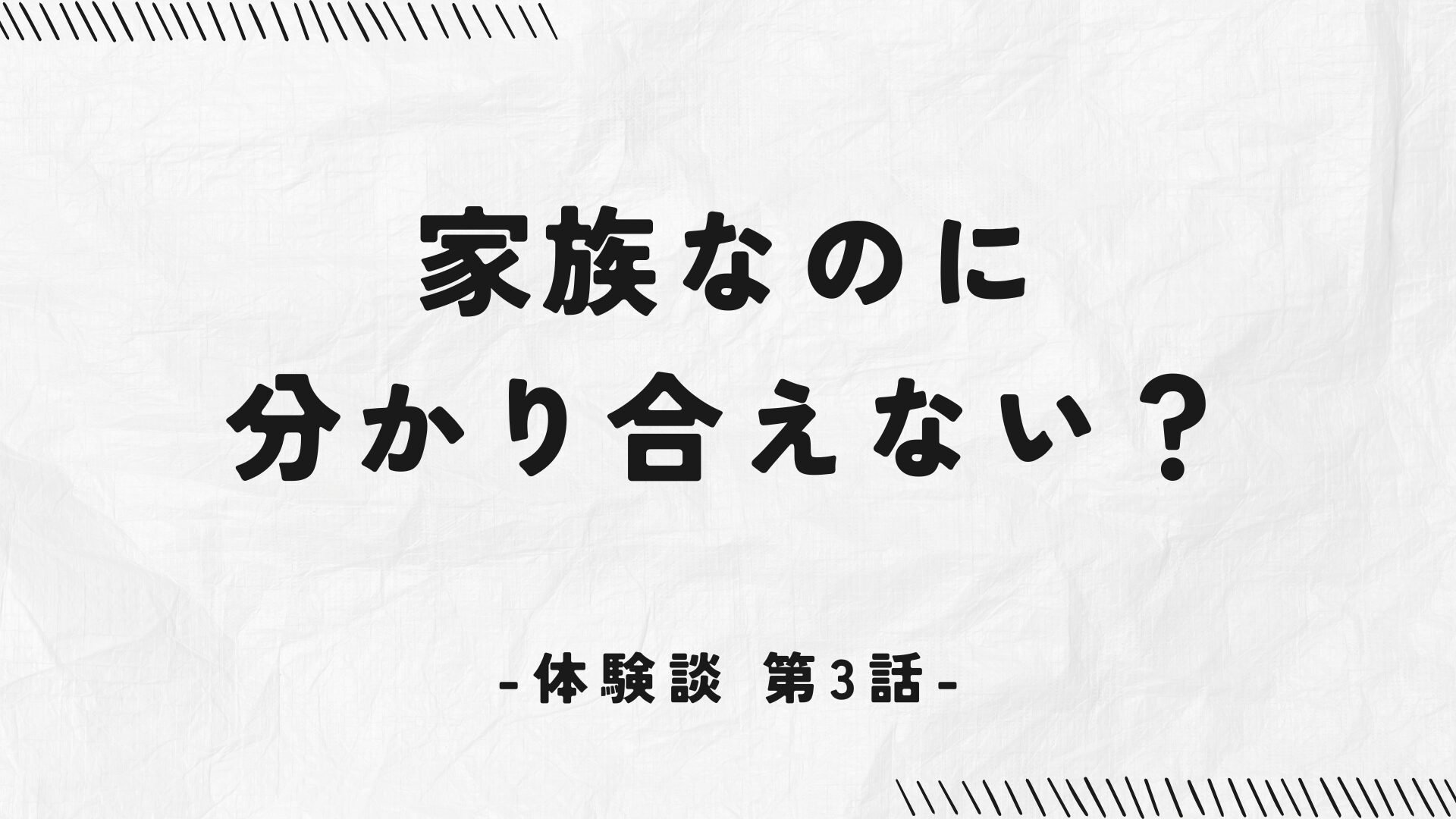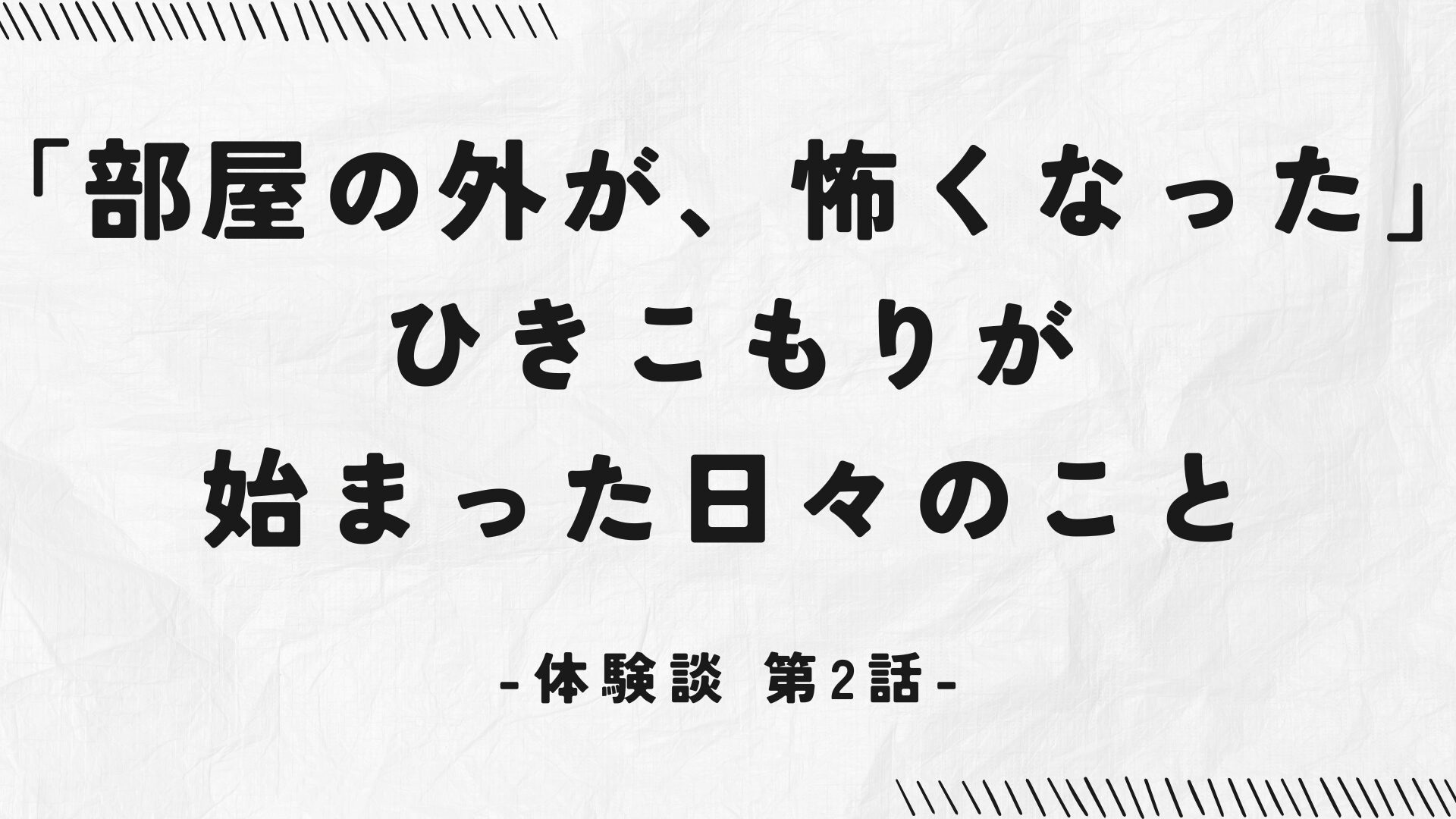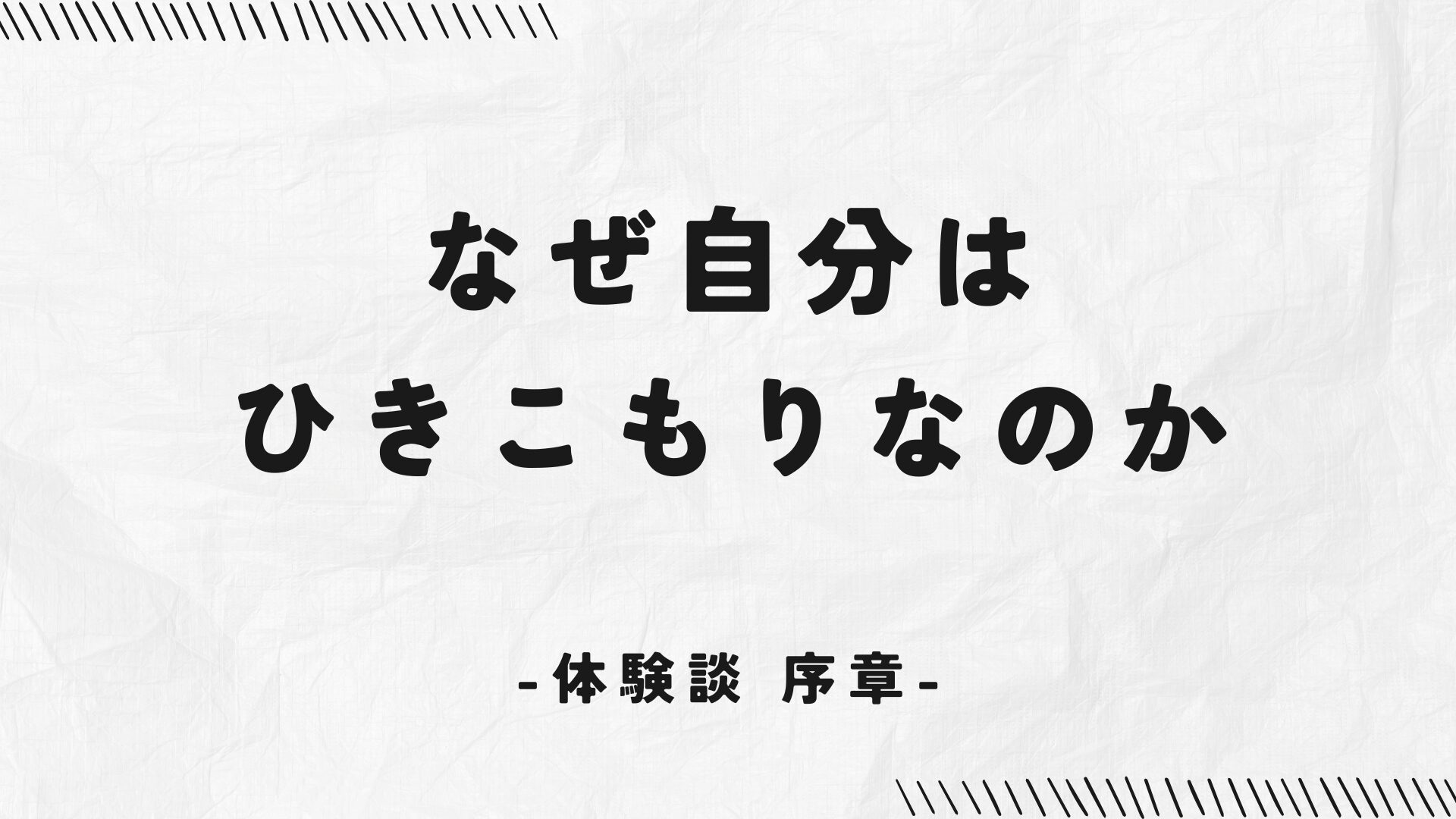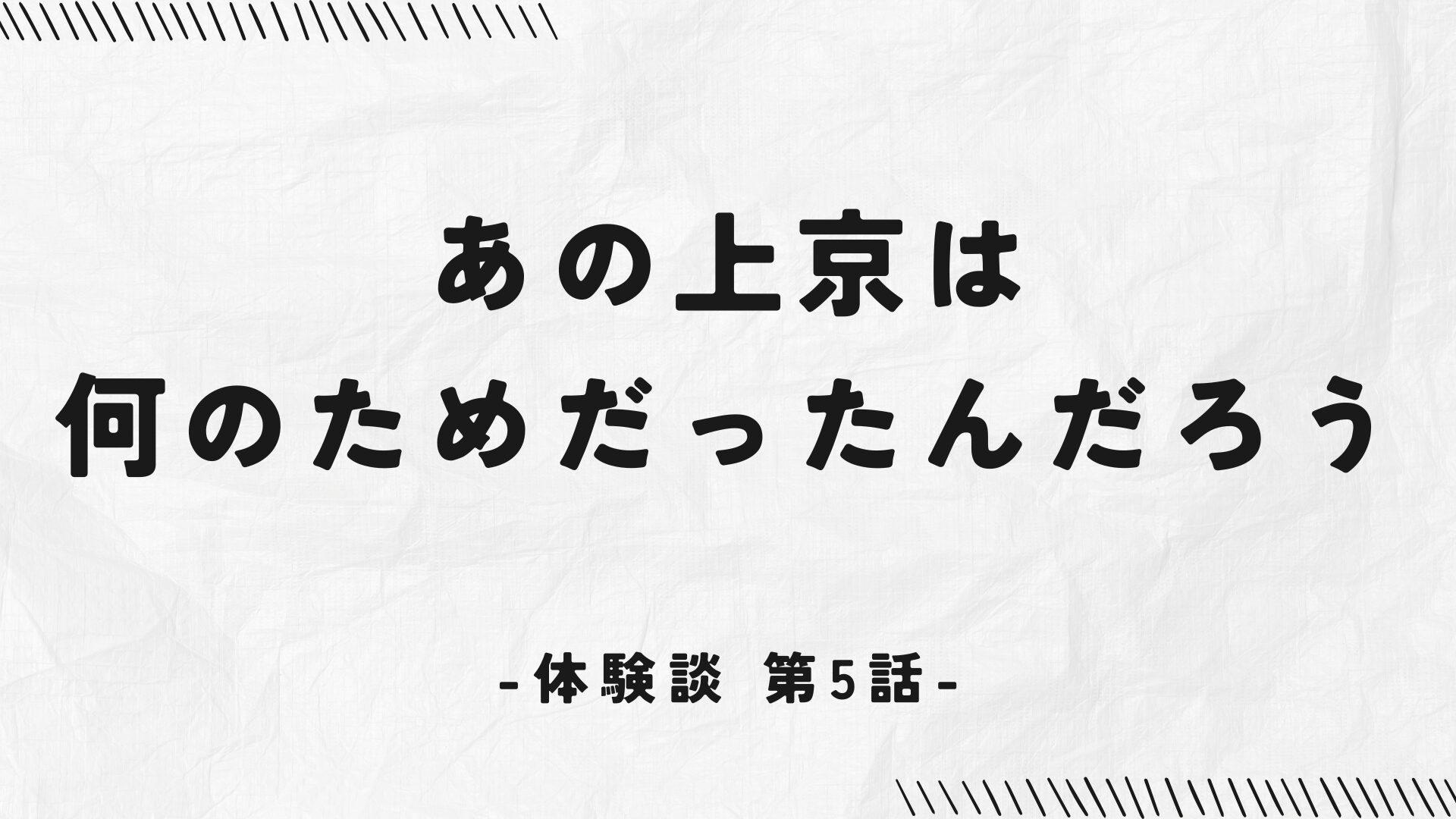第1話:学校で“みんなと同じ”が、できなかった
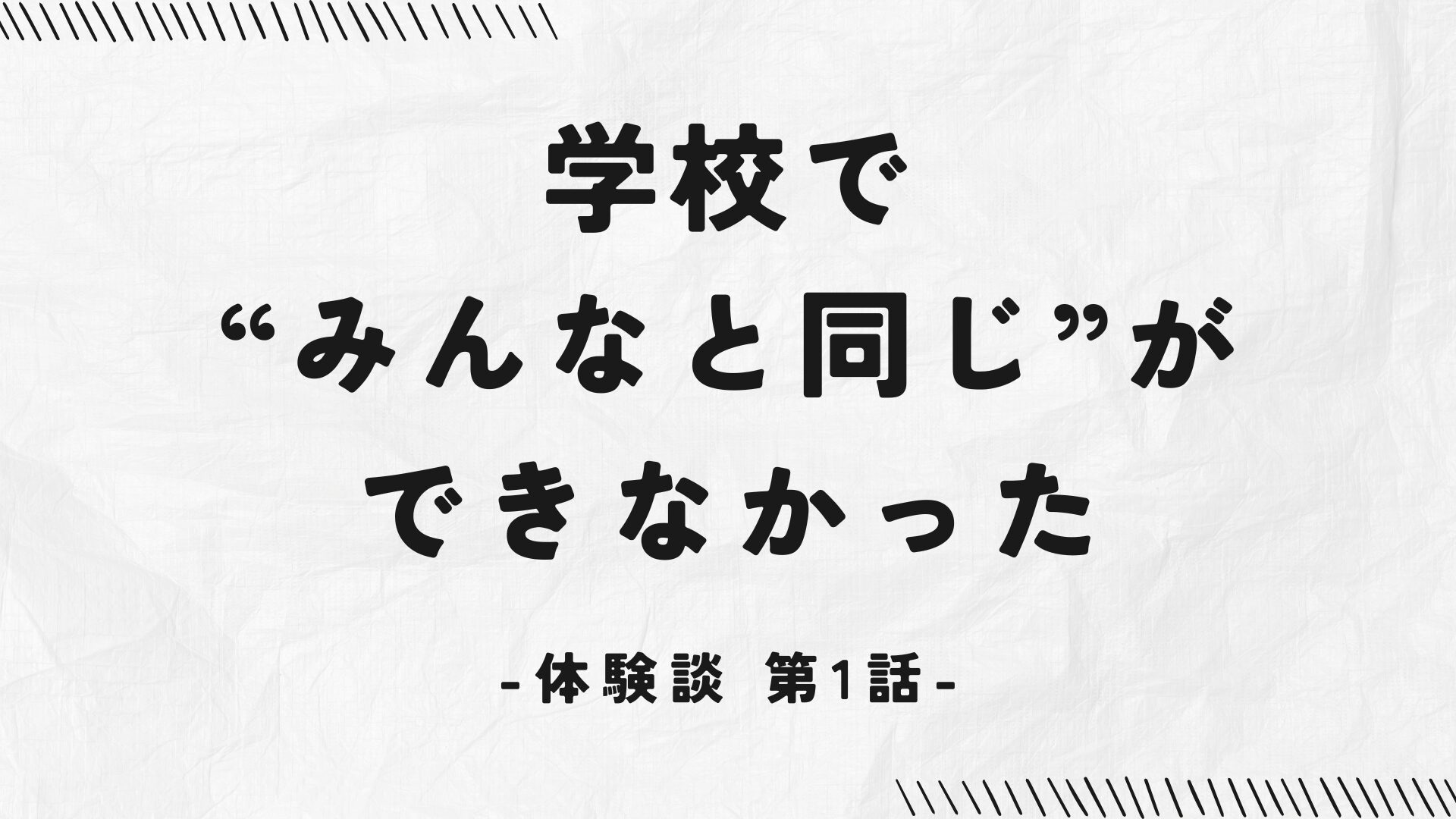
―第1章:ひきこもりのはじまりー
あの頃の自分を振り返ると
今振り返ると、子どもの頃の自分は「どこにでもいる普通の子」だったように思います。
小学生の頃は、スポーツ少年団でバスケをして、公園で遊んで、友達の家でゲームをして過ごす日々。今じゃ考えられないかもしれませんが、神社でかくれんぼや缶蹴りをして遊んでいました。
とにかく、外で誰かと一緒に過ごすのが楽しくて仕方なかったんです。
中学生になるとサッカー部に入って、弱小チームながらも仲間と過ごす時間が楽しくて。「学校って、けっこう楽しいじゃん」なんて思っていたのも、この頃だった気がします。
……でも、高校受験のころから、うっすらと違和感が生まれました。
「なんだか、みんなと同じようにできないかもしれない」
はっきり言葉にできないまま、でも確実に、何かがズレ始めていたんです。
思えばこれが、ひきこもりになるまでの長い旅路の、最初の“つまずき”だったのかもしれません。
そんな自分が何を感じ、どう悩み、どんなふうに変わっていったのか。
その過程を、少しずつ言葉にしていこうと思っています。
楽しかった中学生活と、その先にあった高校という壁
外で遊ぶのが好きだった自分
小学生の頃からずっと、友達と遊ぶことが自分にとっての“楽しみ”でした。
活発で、誰かと一緒に過ごすのが心地よかった。公園でも、神社でも、友達の家でも、誰かと関わる時間が自然と日常に溶け込んでいました。
中学生になっても、その延長のように、部活や放課後の時間を仲間と過ごしていました。弱小ながらサッカー部で汗を流し、友達とふざけ合い、自然体のままでいられる毎日。
「友達がいて、居場所があること」は、自分にとっては当たり前で、特別意識することもありませんでした。
今思えばそれは、安心感に包まれた、違和感のない日常だったんだと思います。
でも、当時の自分には、そんな毎日が「続かないもの」になるなんて、想像もしていなかったんです。
高校受験と漠然とした進路選択
高校受験を迎えたとき、これといった夢があったわけではありませんでした。
ただ「大学には行ったほうがいい」となんとなく思っていて、「だったら進学校に入っておこうかな」という、曖昧な気持ちで高校を選びました。
結果的に合格はしたけれど、「ここに行きたい」という強い思いがあったわけではありません。
大人たちはよく言いました。「高校に行けば将来が広がる」「受験は通過点だ」と。
でも、当時の自分にはその言葉がどこか遠くの話のように聞こえて、心にはあまり響かなかった。
だからなのかもしれません。
高校に入ってすぐ、「自分はなんでここにいるんだろう?」という気持ちがじわじわと湧いてきたんです。
クラスメイトたちは楽しそうに新生活をスタートさせているのに、自分だけが取り残されているような感覚。
スタート地点から、もうすでに違っていたような気がして。その違和感が、より一層、孤独を濃くしていきました。
“みんなと同じ”ができない自分に気づいた日々
知らない人ばかりの教室で
知らない人ばかりの教室。
中学までとは違い、ほとんどが初対面の人たちばかりのクラスに、自分はポツンと立っていました。
毎日を過ごすのは、思っていた以上にしんどいことでした。休み時間も昼休みも、どうやって周りと接すればいいのか分からず、ただ時間が過ぎるのを待つばかり。
それは、自分にとって「居場所がない」という感覚を初めてはっきりと意識した瞬間でもありました。
そしてこの頃、自分は「人見知りなんだ」と初めて気づいた気がします。小中学校のように自然と人に囲まれる環境とは違い、初対面の人ばかりの空間では、自分がどう振る舞えばいいのか分からなかった。
人見知りな自分にとって、クラスという空間そのものが大きなストレスだったのだと思います。
教室にいるだけで肩に力が入り、家に帰る頃にはぐったりと疲れきっている。話しかけられてもうまく返せず、あとから「なんであんな言い方をしてしまったんだろう」と後悔してばかりでした。
そうやって失敗を重ねるうちに、人と話すのがどんどん怖くなっていったんです。
当時の自分は、強がって平気なふりをしていました。でも、本当はずっと「怖い」と思っていた。
言葉を交わすことが、こんなにも心をすり減らすものだなんて、それまでは知りませんでした。
苦しみの正体がわからないまま
周囲の同級生たちは、自然と打ち解け、学校生活を楽しんでいるように見えました。でも、自分にはそれができなかった。
「なんでこんなに苦しいんだろう」
その問いに対する答えは、その時は見つかりませんでした。感情ばかりが先にあって、どうしていいか分からなかったんです。
家に帰っても、誰かにその思いを話すことはできませんでした。自分の中で何かが壊れていくような感覚がありながらも、それをどう表現したらいいのか分からず、言葉にもできないまま心の奥に押し込めていました。
今思えば、あの頃はただ一人で耐えることが「正しいこと」のように思っていたのかもしれません。
今だから言える「ひきこもりのはじまり」の理由
環境の変化、人間関係、目標のなさ
あの頃の高校生活を振り返ってみると、なぜあんなに辛かったのか、大きく分けて3つの要因があったと思います。
- 環境の変化についていけなかったこと
- 人間関係を築くのが苦手だったこと
- 明確な目標がなかったこと
新しい環境に飛び込んだことで、それまでの安心できる関係や習慣が一気に失われてしまい、心が追いついていけなかった。
人と関わることがどんどん負担になっていき、会話ひとつ交わすだけで疲れ果ててしまう毎日。
そして何より、「この場所で、何を目指せばいいのか」が分からなかったこと。
進路も曖昧、目標もなく、居場所も感じられない。そんな状態で過ごす学校生活は、心がすり減っていくばかりでした。
教室にいても、周囲との距離感がつかめず、自分だけがうまく溶け込めていないような感覚。
話しかけられることもあったけれど、どこか居心地の悪さが拭えず、どう振る舞えばいいのか分からないまま時間が過ぎていく。
なぜ自分はこんなにも違和感を覚えるのか、その理由すら分からず、ただ漠然としたモヤモヤが心を占めていました。
そして、朝の登校時間が近づくたびに、行きたくないという気持ちが胸いっぱいに広がっていったのです。
「なぜ」の問いがなかったあの頃
もし、なぜ苦しいのかを自分に問いかけたり、誰かに相談したりできていたら、状況は変わっていたかもしれません。
でも、当時の自分は、その感情に向き合うことすらできませんでした。
感情の奥にある理由を探せば、もしかしたら解決のヒントや支えを見つけられたかもしれない。でもそれを知らなかった自分には、「ただ我慢する」か「逃げる」しか方法がなかったんです。
気がつけば、朝起きるのがつらくなっていました。
布団から出るのに何十分もかかる。学校のことを考えるだけでお腹が痛くなったり、頭が重くなったり、身体にも不調が出るようになっていました。
「学校が自分には向いていないのかもしれない」
そう思うことが増えていくにつれ、その思考は少しずつ自分を追い詰めていきました。
つまずきの記憶から、始まったもの
結局、1年で高校を辞めることになりました。
心の中には、行き場のない不安や戸惑いがずっと残り続けていました。
「みんなと同じ」ができなかったことを、以前はどこか引け目のように感じていたこともありました。
でも今では、それも自分にとって必要な過程だったのだと受け止められるようになってきました。
今ならあの頃の自分に「大丈夫だよ」と声をかけてあげたい、そんな気持ちになります。
この先、どんなふうに過ごし、どんなふうに気持ちが変わっていったのか——
ここから、自分のひきこもり生活と、それをどう乗り越えていったのかを、少しずつ綴っていきたいと思います。
読者への一言
もし今、学校が辛いと感じている人がいたら、あなたのその感情には明確な理由があるかもしれません。
無理に「みんなと同じ」にならなくても大丈夫。
あなたの気持ちは、あなたにしかわからない大切なものです。
それを否定せず、大事にしてあげてほしいと思います。
▶【目次】はこちら→ 元ひきこもりの歩き方|社会復帰ノート
◀【序章】はこちら→なぜ自分は、ひきこもりなのか
▶【第2話】はこちら→「部屋の外が、怖くなった」―ひきこもりが始まった日々のこと