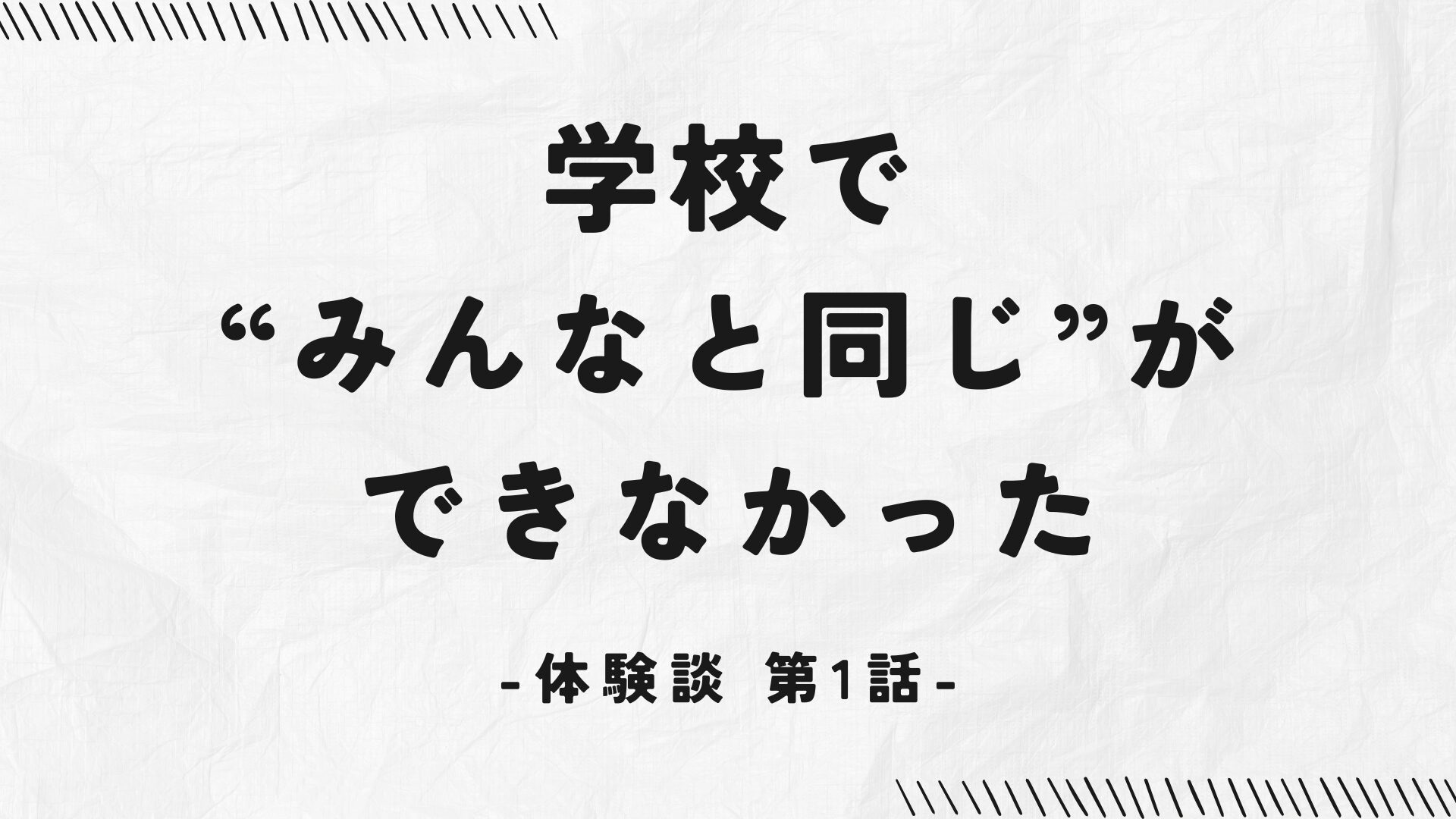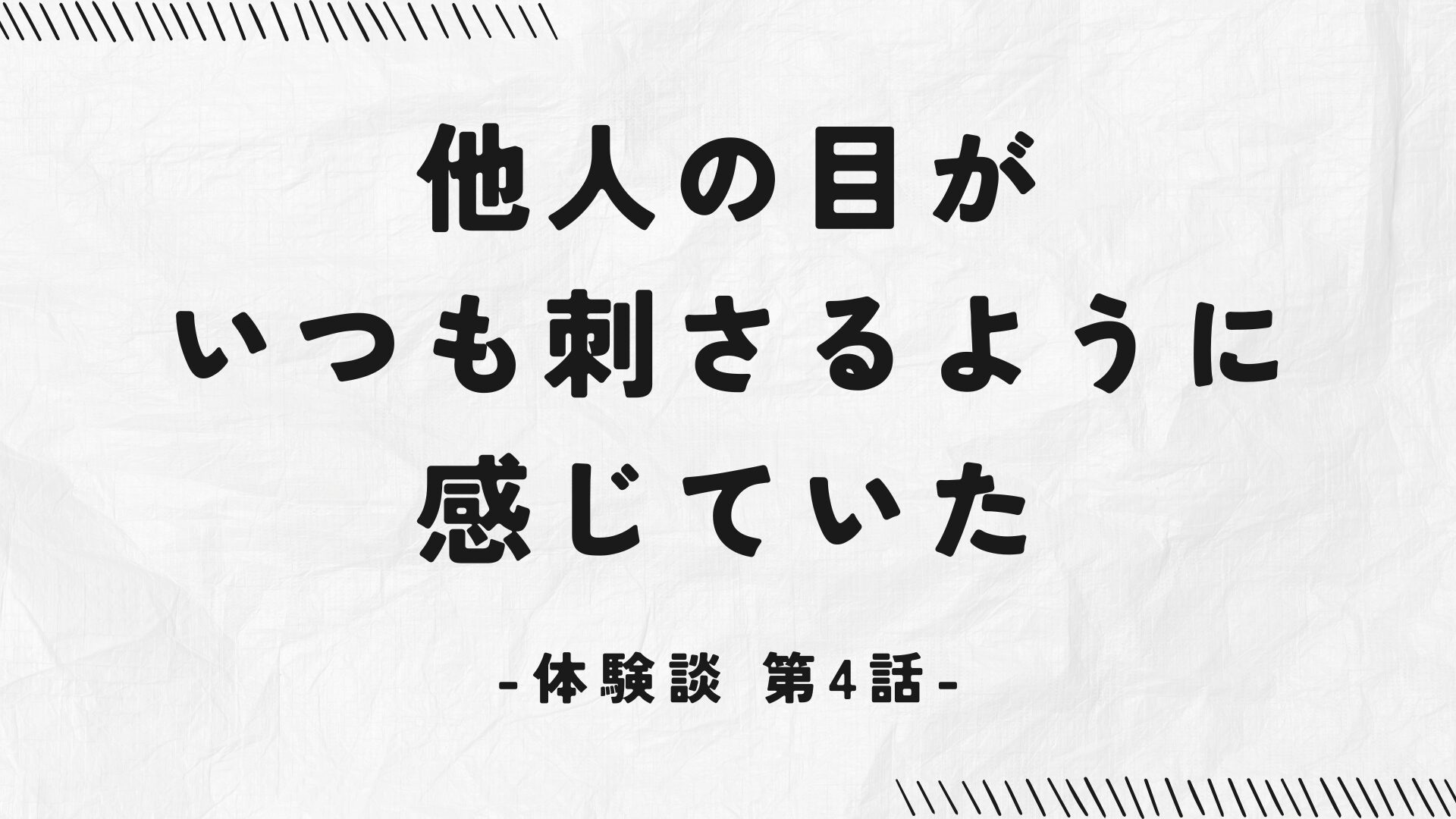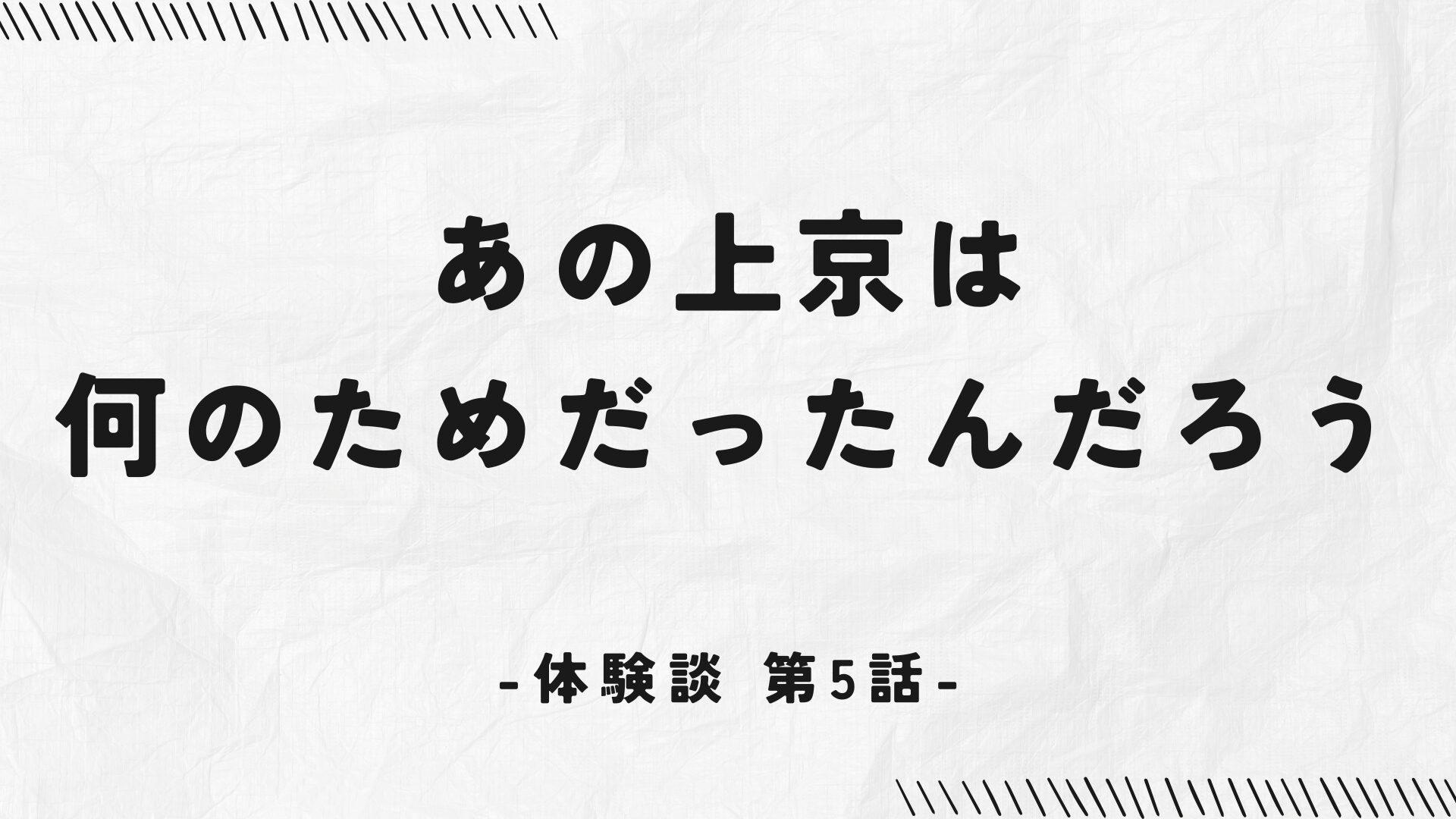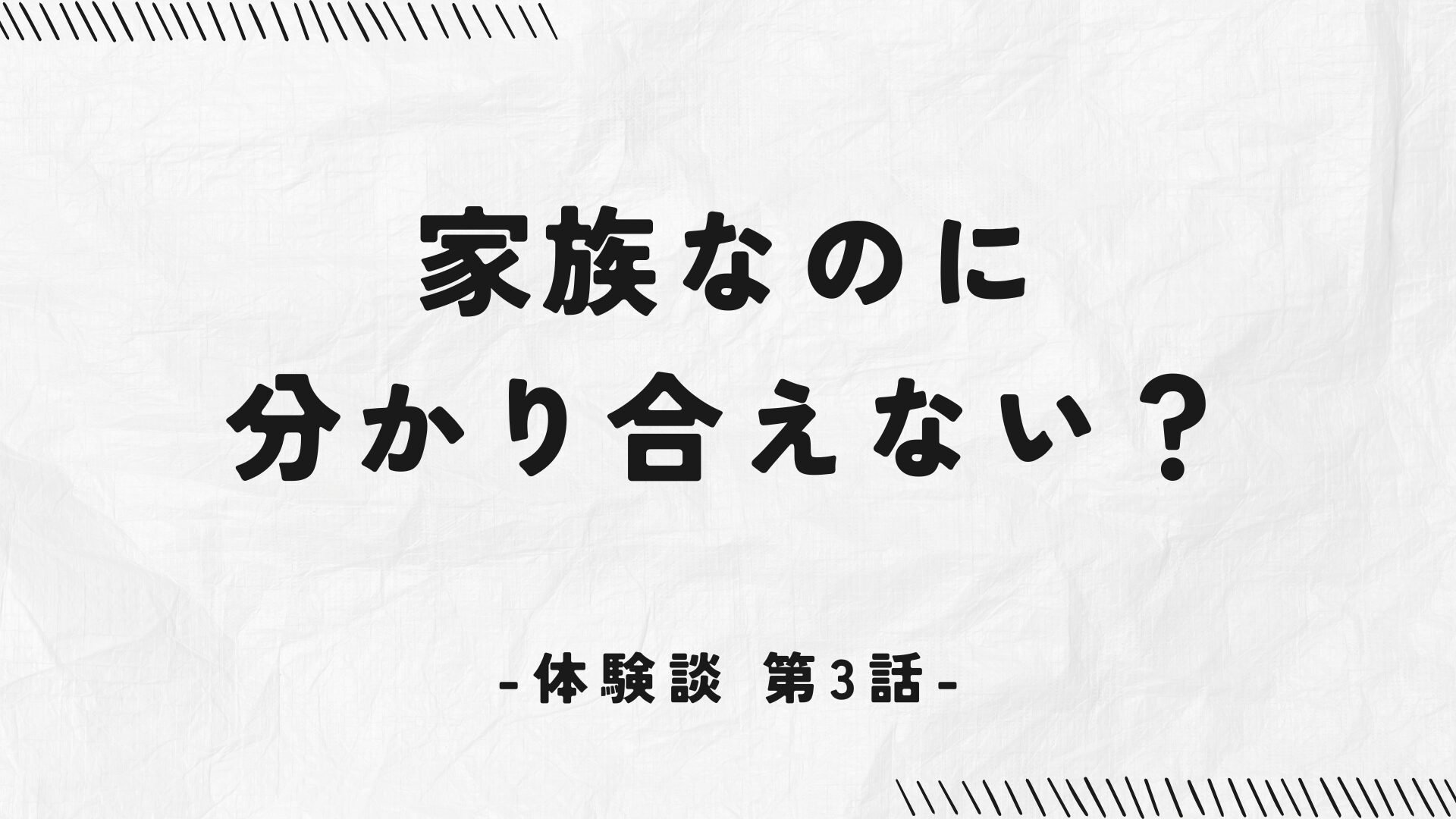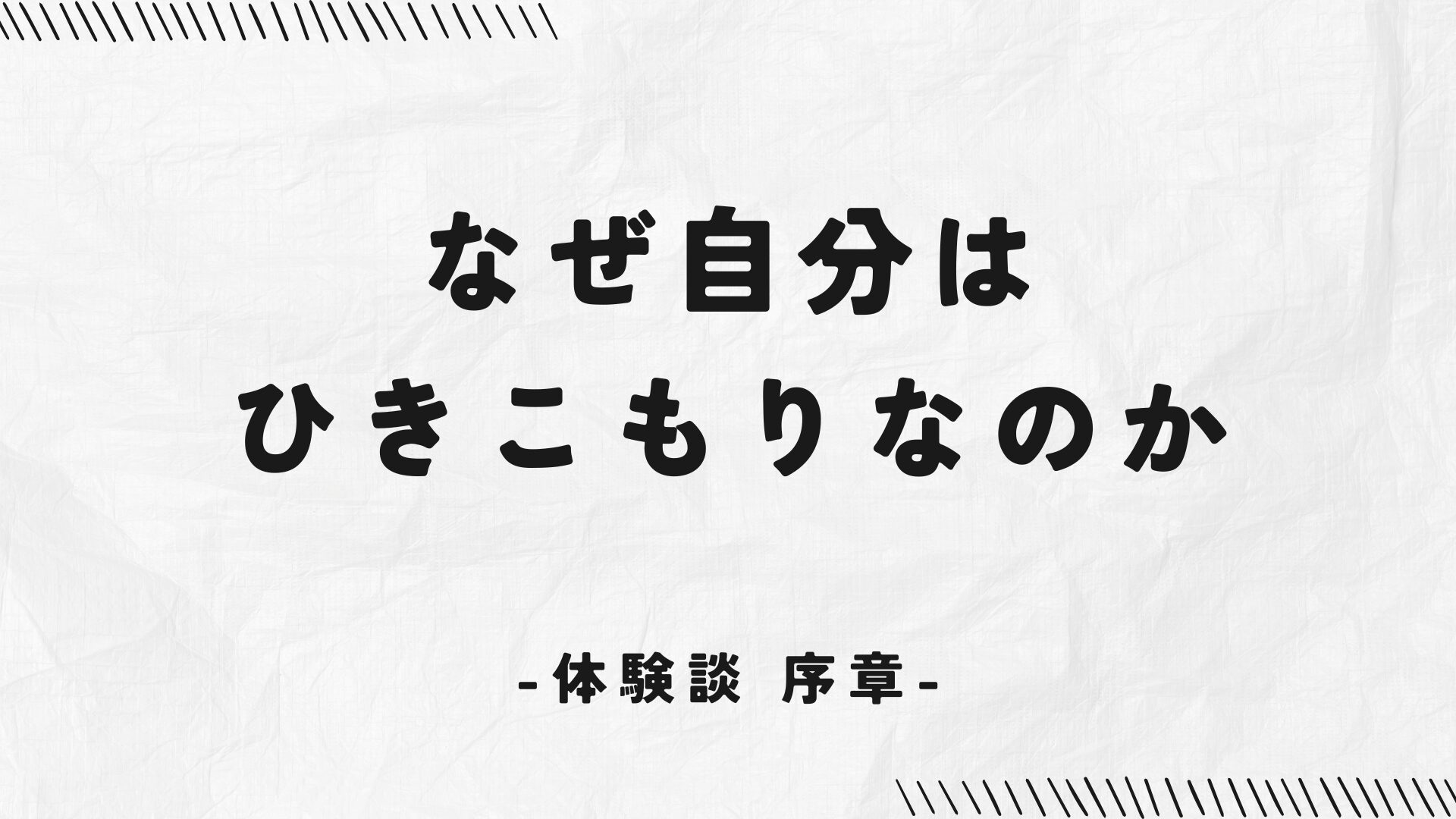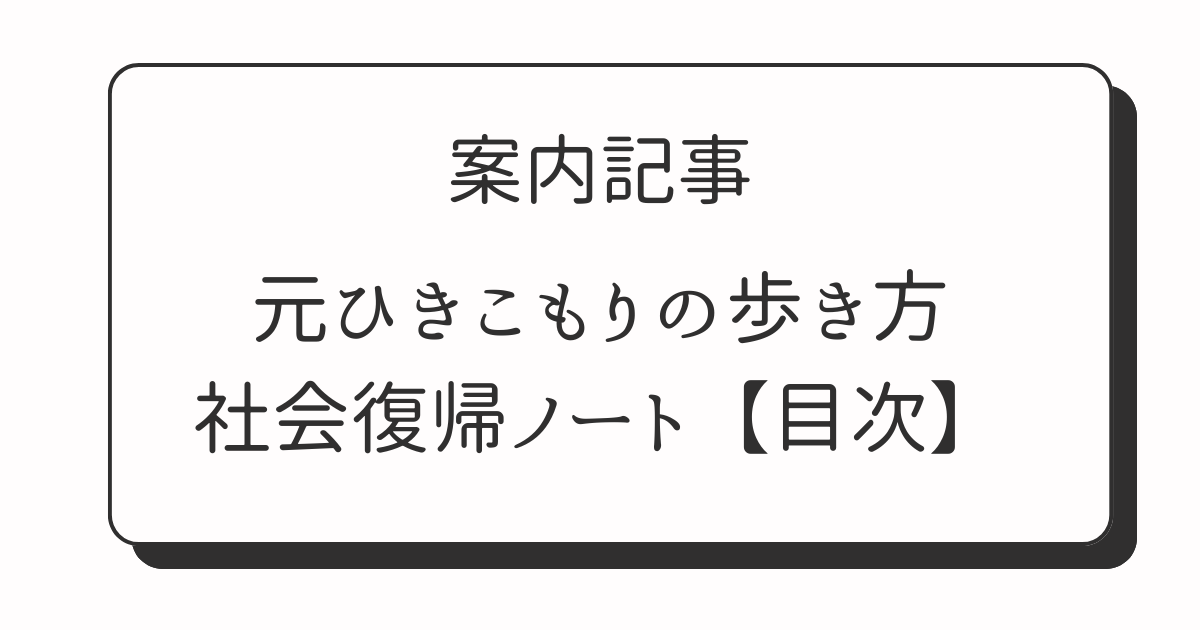第2話:「部屋の外が、怖くなった」―ひきこもりが始まった日々のこと
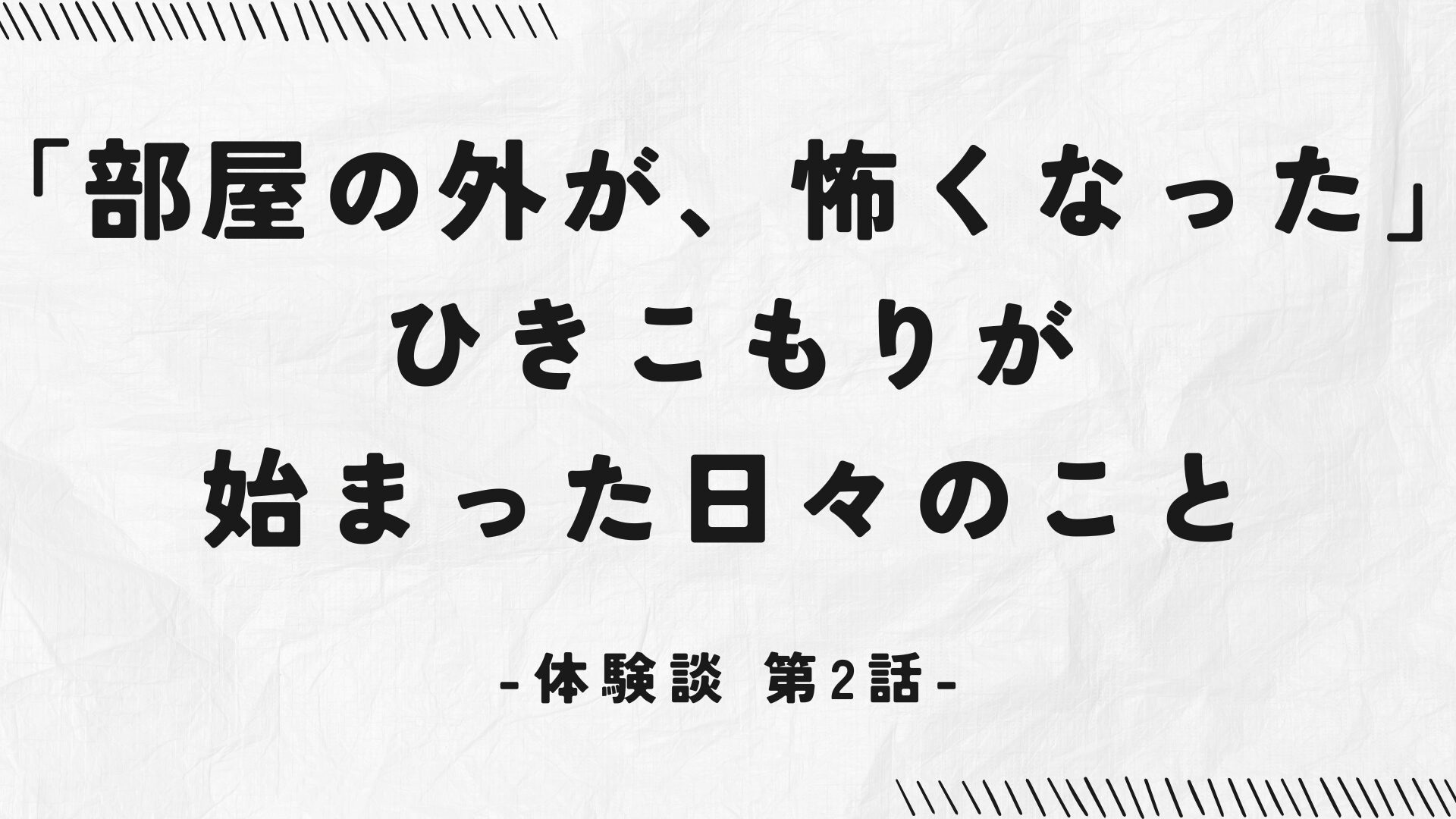
ー第1章:ひきこもりのはじまりー
不登校になった、最初の頃の気持ち
あの日、最初のきっかけは本当に些細なものでした。たとえば、朝起きたときに少し体が重かったとか、なんとなく学校に行く気分じゃなかったとか。そんな「ちょっとした不調」から始まったんです。
「まあ、今日は休んでもいいか」と思ったのが1日目。「明日こそ行こう」と思ったのに動けなかった2日目。そうして休みが続くうちに、教室の扉が遠く感じられるようになっていきました。
教室のざわざわした空気、先生の視線、クラスメイトの何気ない言葉。そんなすべてが、自分を責めるように思えて、ドアノブを握る手が震えるようになったんです。
最初はただの「休み」だったのに、いつの間にか「戻れない場所」になってしまった。あの頃のわたしにとって、部屋の外の世界は、ちょっと怖すぎました。
通えなくなるまでは一瞬だった
本格的に学校へ行けなくなったのは、高校1年の6月頃のことです。
最初のうちは、数日おきに登校したり、「今日は頑張って行こう」と自分を奮い立たせたりしていました。でも、教室に入ると、体がぎゅっと強張ってしまうんです。周りの声や笑い声が、自分とは別の世界のもののように聞こえて、どこにいても居場所がない気がしていました。
そんな日々が続くうちに、朝が来るのが怖くなっていきました。「今日も学校に行けなかった」という自己嫌悪が積み重なって、ついにはまったく足が向かなくなったんです。
「通えなくなる」なんて、もっと劇的なきっかけがあると思っていた。でも実際には、静かに、じわじわと、気づいたらもう戻れなくなっていた。あれは本当に、一瞬の出来事だったように感じます。
友達が来てくれたけれど
中学時代の友達が、自分の家を訪ねてくれたことがありました。その気持ちはすごく嬉しかった。でも、そのときの自分は、不登校になったことが恥ずかしくて、どうしても顔を合わせる勇気が出ませんでした。
インターホンが鳴っても、返事をせずに息をひそめる。カーテン越しにそっと外を覗いて、誰が来たのかを確認しながらも、ドアを開けることはできませんでした。窓の外に立つ友達の姿を見つけても、心がざわついて、体が動きませんでした。
自分の部屋は一階で、窓のすぐ外は道路に面しています。車の音、人の足音、チャイムの音——そんな日常の音が、ある日突然、すべて怖いものに変わったんです。
家で過ごす日々が、当たり前になっていった
単調な日々の繰り返し
ゲームをする。アニメを見る。ネットサーフィンをする。昼の情報番組をぼんやり眺める。そして、母が作ってくれるご飯を食べる。
家の中での生活は、そんな限られた選択肢のなかで成り立っていました。やることは数えるほどしかなくて、毎日が同じように過ぎていきました。
気がつけば、部屋にこもる時間がどんどん長くなっていき、それが「普通」になっていったんです。朝が来ても、外に出る理由はなくて、夜が来ても、眠るタイミングも曖昧で。曜日の感覚もなくなっていきました。
窓の外の時間だけが流れているようで、自分はその流れの外にぽつんと取り残されているような、そんな感覚に包まれていました。
外に出ることへの怖さ
気分転換に少し外に出てみようと思ったこともありました。でも、外の空気に触れた瞬間から、学校の生徒や同級生に見られるかもしれない、そんな不安でいっぱいになるんです。
そそくさと買い物を済ませて、なるべく人目につかないように、さっと帰る。その繰り返しでした。
ある日、うっかり学校の下校時間と重なって外に出てしまったことがありました。そのとき、同級生に声をかけられたんです。
せっかく声をかけてくれたのに、自分はうつむいて無視してしまいました。不登校であることが恥ずかしくて、言葉が出てこなかったんです。今でもあの瞬間が、心のどこかに残っています。
もともと住んでいた場所は田舎で、知り合いに出くわす確率も高かった。だからこそ、外に出ることへの怖さは増していきました。
玄関のドアを開ける前でさえ、耳をすませて外の気配を探るようになっていました。まるで誰かに見張られているかのように、いつもびくびくしていたんです。
あのとき、なぜそこまで恥ずかしかったのか
「不登校=悪いこと」「こんな自分はダメなんだ」——そう思い込んでいたことが、自分の恥ずかしさの正体だったように思います。
声をかけてくれた相手を無視してしまったこと、それへの後悔。そして、また同じような場面で自分はどう振る舞えばいいのか分からないという不安。それらが積み重なって、人と関わることそのものが、どんどん怖くなっていきました。
そんなふうにして、自分はますます「ダメな存在」に思えていき、心の距離はどんどん広がっていきました。
田舎という環境も影響していたと思います。一人で外を歩いているだけで、誰かに見られているような気がしてしまう。都会のように人が多ければ、誰が誰だか分からない安心感もあったのかもしれません。
でもあの頃の自分には、部屋だけが、唯一安心できる場所でした。
まだ「ひきこもり」だという自覚もないままに、自分の世界はどんどん狭くなっていったのです。
今なら、あのときの自分がなぜ動けなかったのか、どう行動すればよかったのか、少しずつ理解できるようになってきました。
▶【目次】はこちら→ 元ひきこもりの歩き方|社会復帰ノート
◀【第1話】はこちら→学校で“みんなと同じ”が、できなかった
▶【第3話】はこちら→家族なのに、分かり合えない?