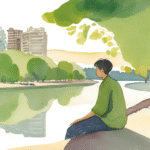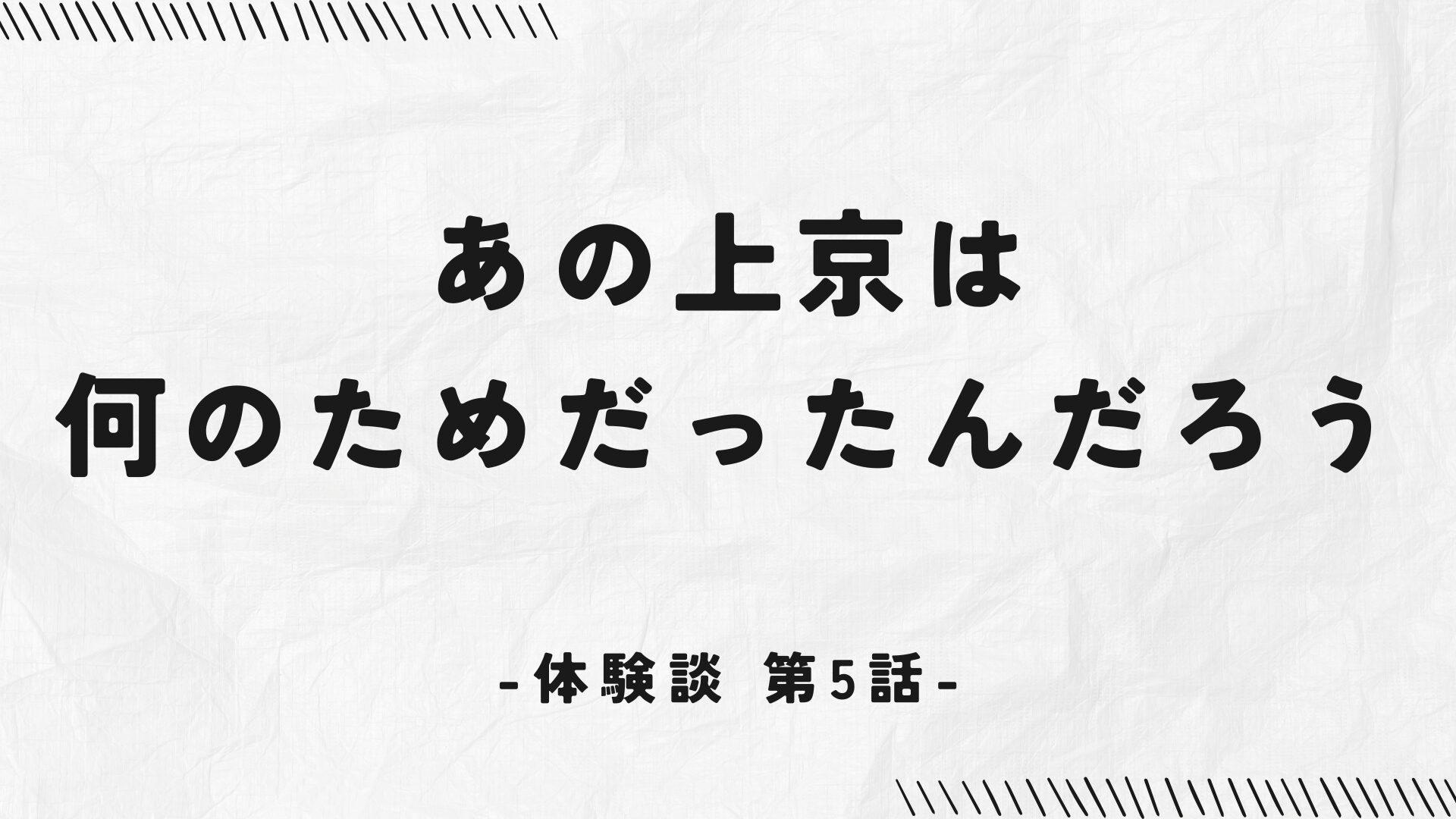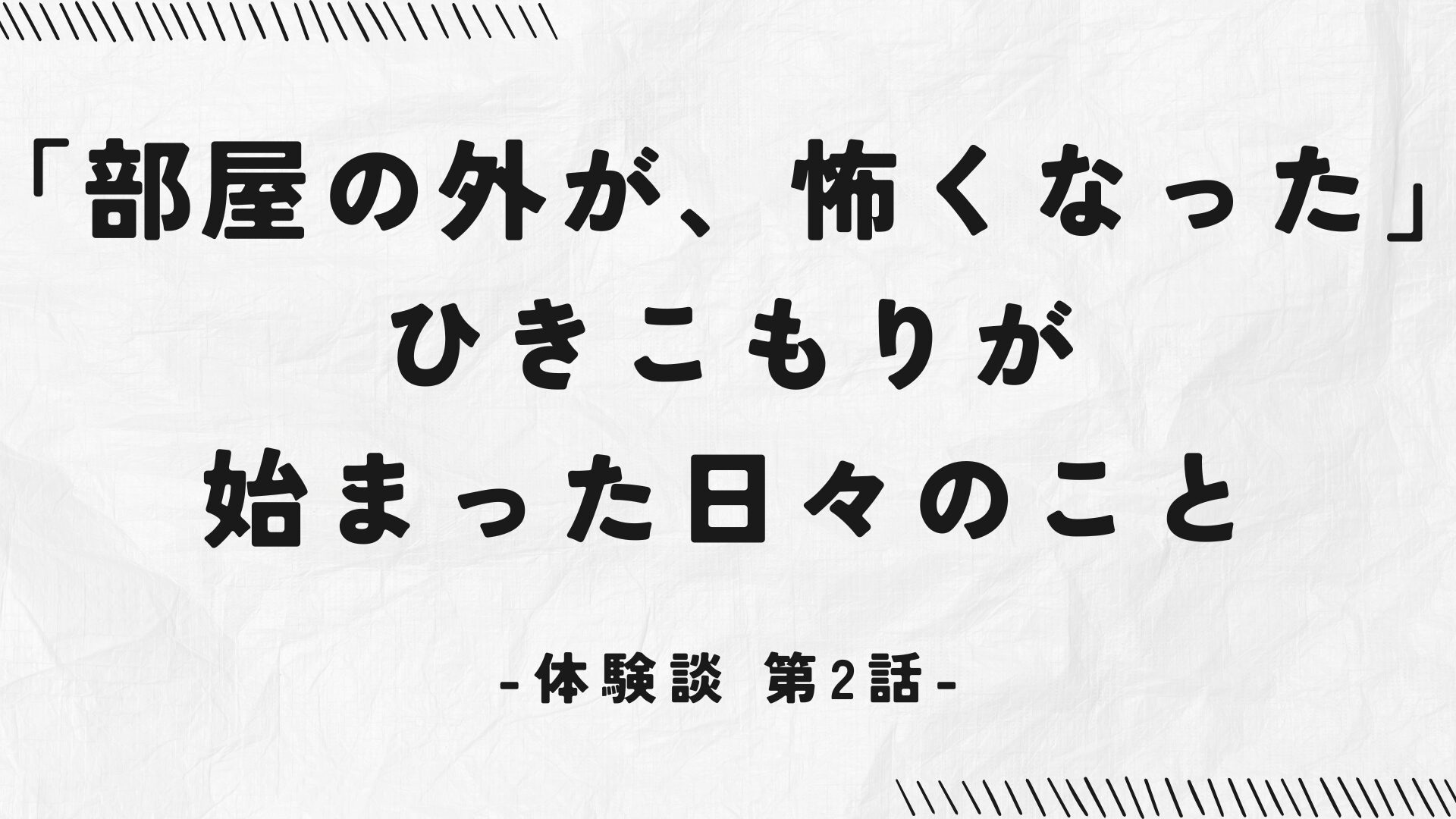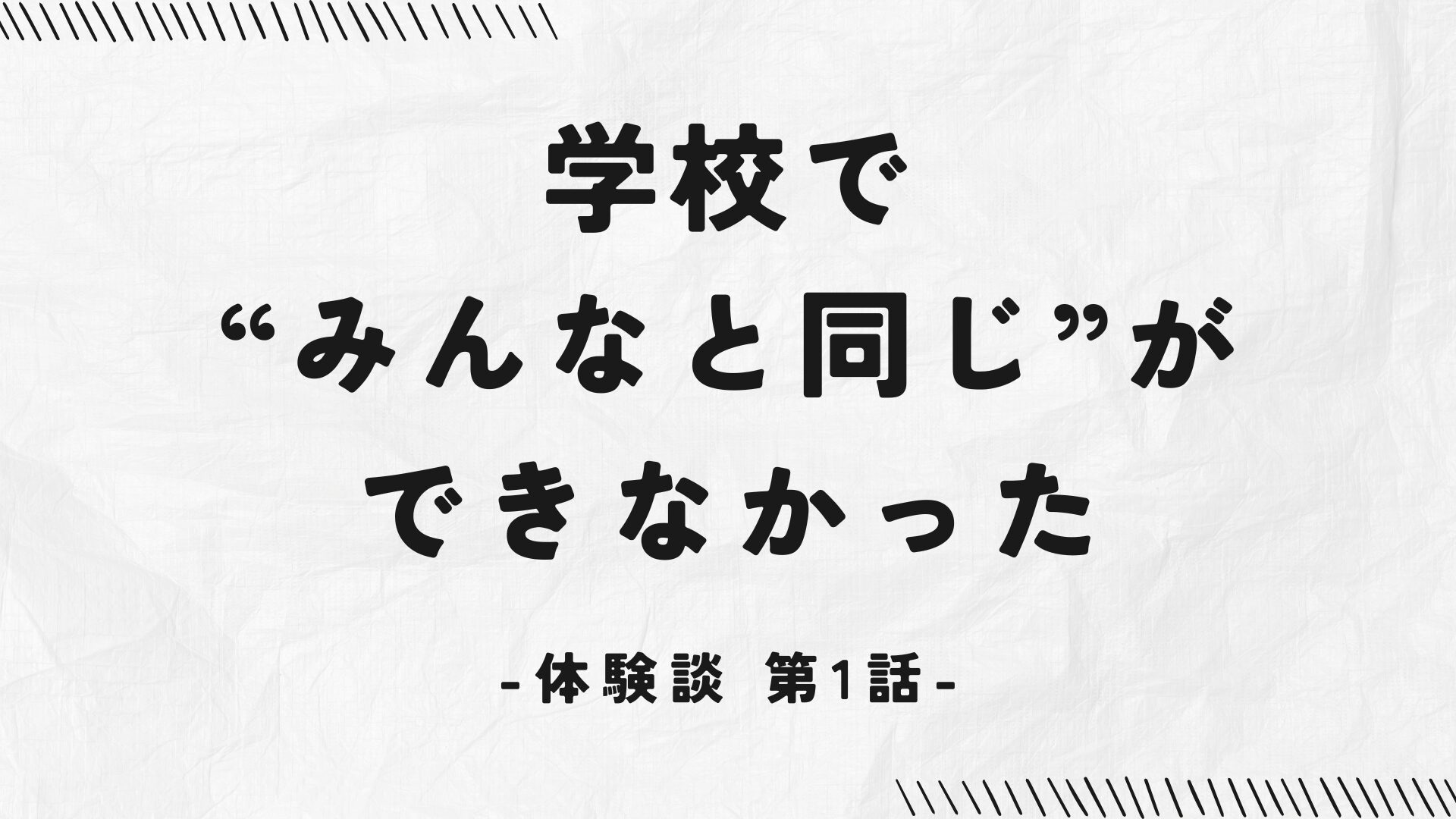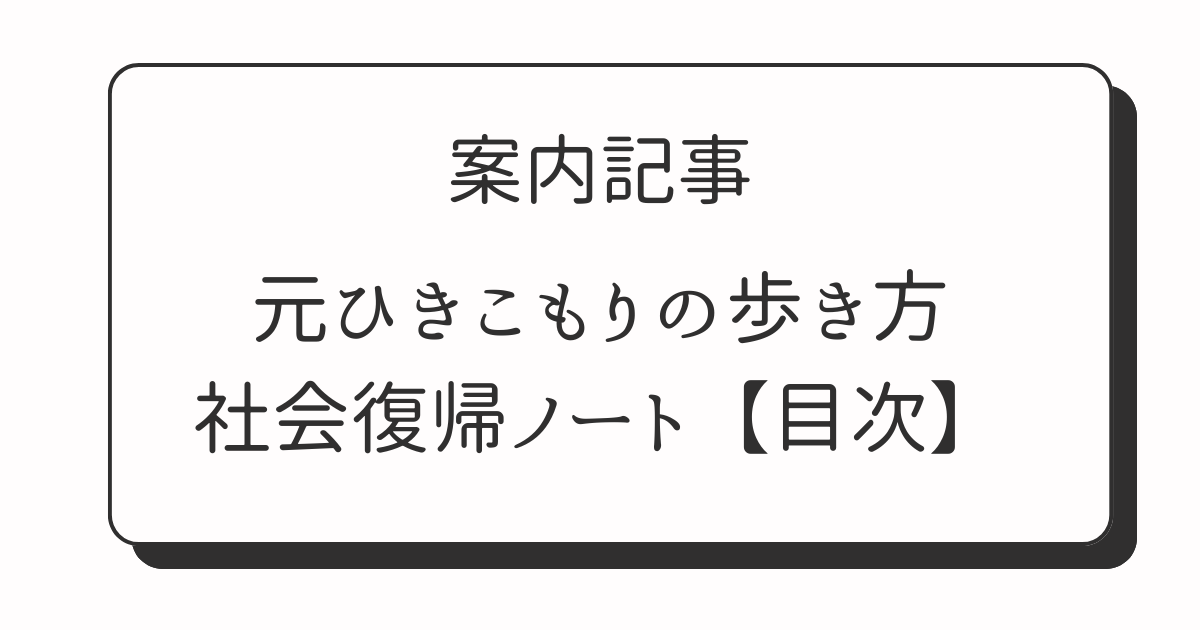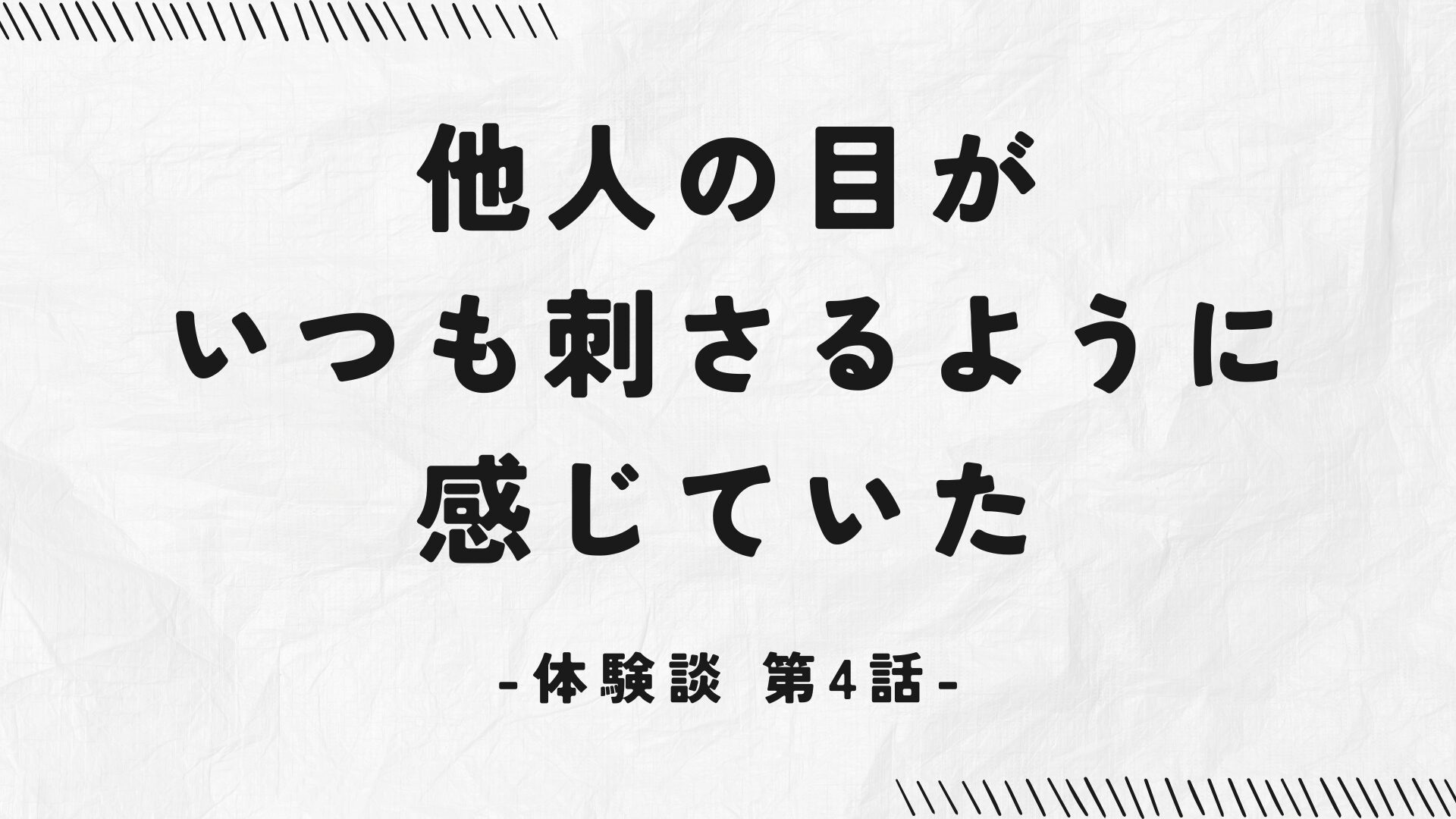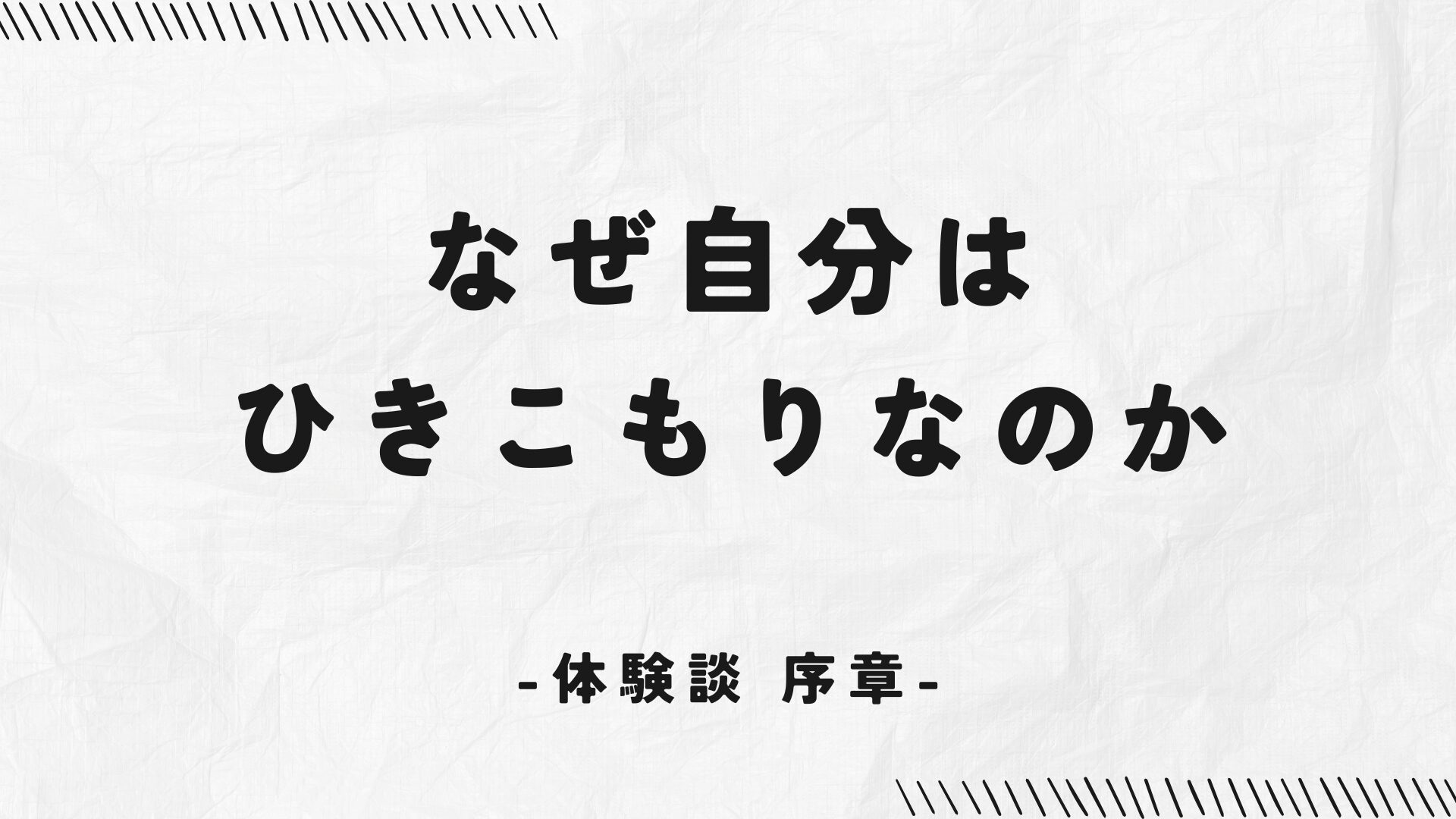第3話:家族なのに、分かり合えない?
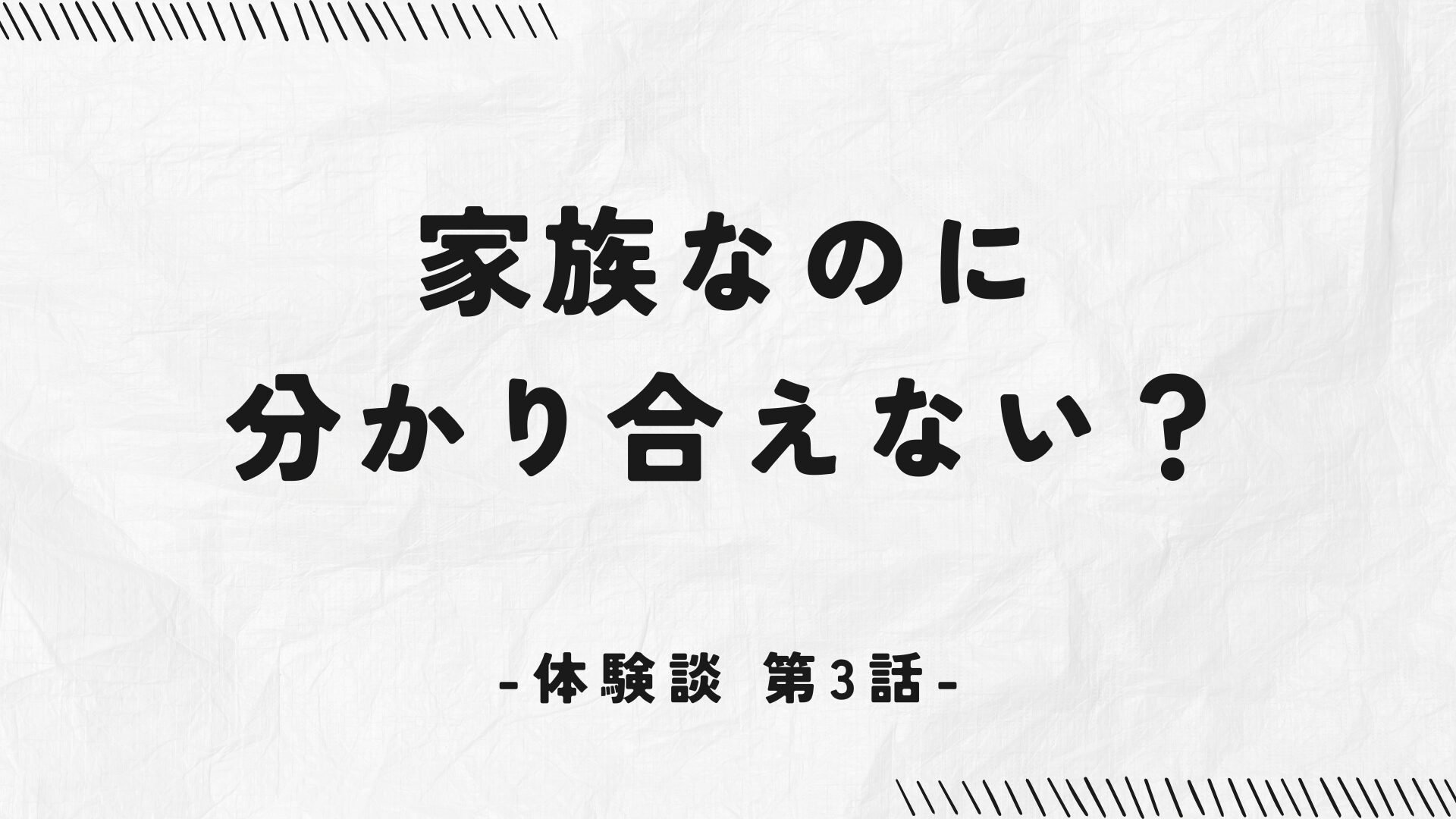
ー第1章:ひきこもりのはじまりー
親の離婚と自分の選択
中学2年、家族がバラバラになった日
自分が中学2年生の頃、親が離婚しました。
それからは自分、父、祖母の3人での暮らしが始まりました。母がいなくなった家は、なんとなく散らかった雰囲気がありましたが、中学生だった自分はそこまで気にしていませんでした。
食事もだんだんとワンパターンになっていった気がしますが、それでも毎日お弁当を作ってくれた父には、今となっては本当に感謝しています。当時はそれが当たり前だと思っていましたが、自分でご飯を作るようになった今、あの頃の父の苦労がわかるようになりました。
当時、自分は今通っている中学校を変えたくないと思い、父親と暮らすことを選びました。姉は母の方に行き、たまに母と姉の住むアパートに行って、ご飯を一緒に食べる。そんな生活が続きました。
何気ない選択が分岐点だったのかもしれない
今思えば、あのときの選択が、その後の自分の在り方に影響していたのかもしれません。
高校に進学してから、自分は“環境の変化”にうまく馴染めなかった。でもその兆しは、すでに中学の終わり頃にあったのかもしれないと思うのです。
もし、あのとき中学校を転校していたら。
新しい環境に飛び込んで、新しい人間関係の中で過ごすという経験を、早い段階でしていたら。
それが、高校での「変化」にもう少しうまく対応できるきっかけになっていた可能性もあるのではないか──そんなふうに考えることがあります。
もちろん、転校先でうまくいかなかったかもしれないし、逆にもっと孤独だったかもしれない。だから、「あっちのほうがよかった」と言いたいわけではありません。
ただ、「環境の変化に向き合う」という経験。それが自分には、少し足りていなかったのかもしれない。
そんな気がするのです。
高校進学、母との暮らしが始まる
理由は「近いから」だったけど
中学校を卒業してから、自分は母と暮らすことになりました。
その理由はとてもシンプルで、「高校が近いから」でした。
姉は大学進学で都会へ出ていき、家には母と自分のふたりだけ。電車に乗って通うよりも、歩いて通える距離にある母の家のほうが、明らかに楽だった。
それだけの理由で決めたはずだったのに、その選択が、自分の生活を大きく変えることになりました。
今になって思うのは、もし電車で通っていたら──中学の同級生と顔を合わせる機会がもっとあったかもしれないということ。
くだらない話を交わすだけでも、心が少し軽くなったかもしれない。あのときの自分には、そんな「つながり」の価値が、まだよくわかっていなかった。
人とつながれるって、すごく大切なことです。
それは、家族だって同じで。話せる相手がいるだけで、自分を支えてくれる存在になる。
それを、あの頃の自分は知らなかっただけなのかもしれません。
部屋にこもる自分と、母との距離
話さない、でも同じ家にいる
それでも当時の自分は、何もできないままでした。母に対しても、どこか素直になれない時期。
反抗期が終わったようで終わっていない、そんな中途半端な感情のなかで、大人との距離をとりたがっていた自分がいました。
このとき、母は何を感じていたんだろう?
ほとんど会話もなくて、自分は部屋にこもりきり。ご飯の時間にはリビングに出ていたと思うけれど、どんな話をしていたのか、まるで思い出せません。
今、思い出せるのは、部屋でどんなゲームをしていたかとか、どんなアニメを観ていたかとか。延々とネットサーフィンして、時間をつぶしていたことばかりです。
今だから思う、家族との関係
今ならわかります。自宅にいる自分にとって、外に出るきっかけを与えてくれる存在は、家族でしかなかったということを。
もちろん、ネットがあればいくらでも情報は手に入るし、娯楽もあります。もしかしたら、そうしたものから何かやりたいことが見つかることもあるかもしれません。
でも、「外に出る」という一歩を踏み出すには、どうしても、誰かの存在、あるいは何かの支えが必要なんです。
その話は、また次の章で触れていきたいと思います。きっかけになったのは、まだ先の話ですが、母の言葉でした。
家族なのに、言葉を交わすのが難しかった時期。でも、あの時間も、今の自分をつくるうえで大切な時間だったのかもしれません。
◀【目次】はこちら→ 元ひきこもりの歩き方|社会復帰ノート
◀【第2話】はこちら→「部屋の外が、怖くなった」―ひきこもりが始まった日々のこと
▶【第4話】はこちら→他人の目が、いつも刺さるように感じていた